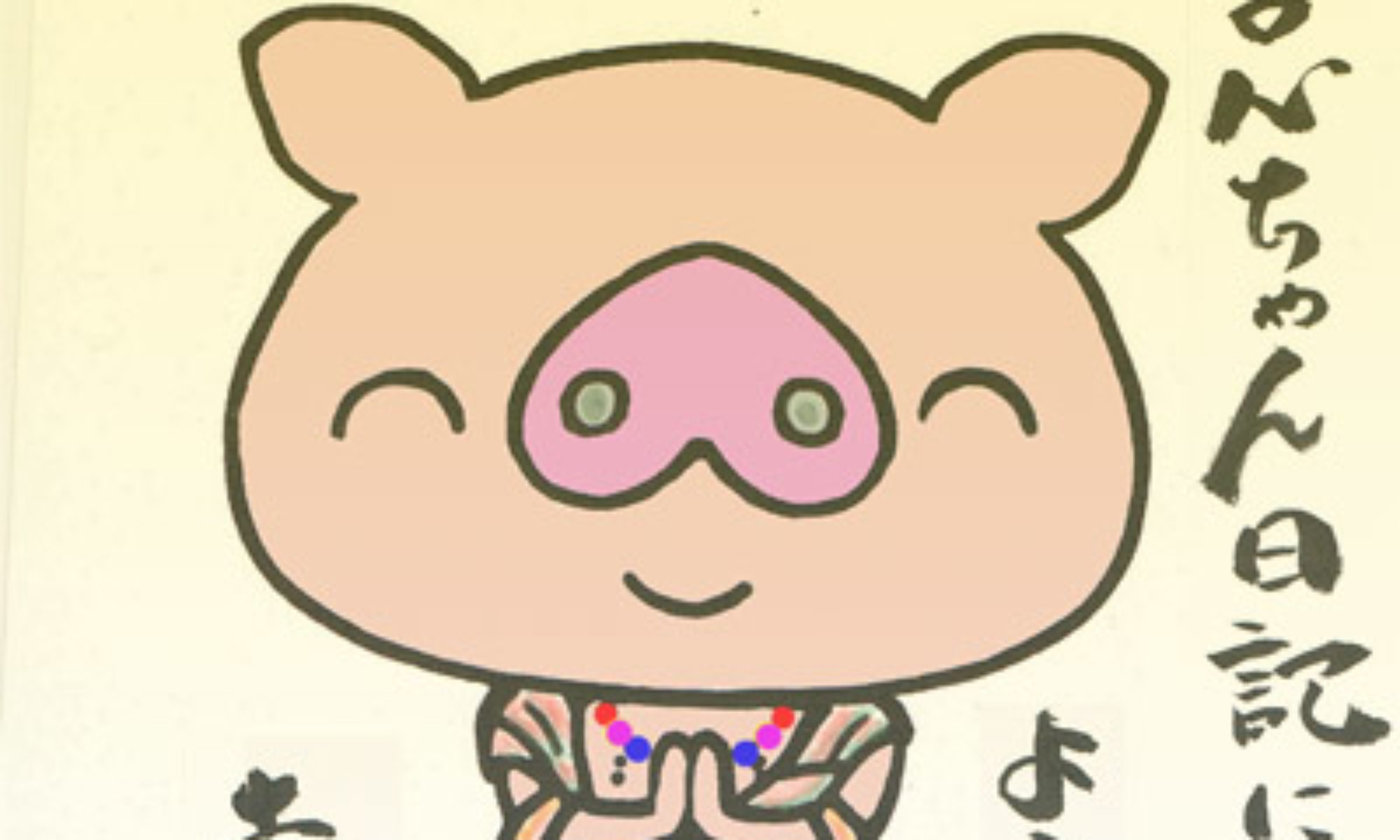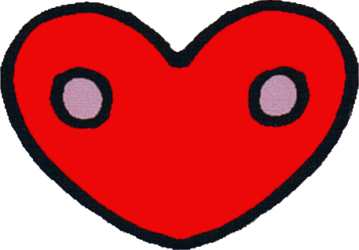夕立という死語
死語という言葉にはいささか言いすぎの感もある。
子供の頃、横浜の田舎であったけれど、夕方になると決まって雨が降った。
それもにわかに掻き曇り、ザー・・・っと降ってくる。
けれど子供たちは慣れたもので、ちょっと軒先を借りて雨宿りする時間で雨はすぐに上がることを心得ていた。
さっきの雨は何処に行ったやら・・・
雲間に夏の太陽は再びかえる。
つくつくぼうしが鳴き始め、夕刻の涼しさのうちに戸張が落ち始める。
今はその常識が全く役に立たなくなった。
「夕立」気温を下げてくれる、かつ夕刻を教えてくれた恵みのスコールであったのだ。
なぜ?降らぬ。
全く降らない。
降ればふったで、「ゲリラ豪雨」と呼ばれてしまった。
とても恵みとは縁遠く気難しい代物に成り果てている。
おっかしいなぁ・・・
日本人の・・・
(いやいやそう言うと角が立つかな)
僕自身も含めてややこしくなったこの時代に生きるものと歩調を合わせるように雨も気難しくなったと見える。
情緒をすら醸し出す夕立とやらには、もう逢えないものなのだろうか。
浅草のそら

天竺無垢玉

27玉の片手念珠を製作するのに必要な玉の大きさは、概ね主玉が10mm、親玉で14mmが必要となります。
通常、天竺菩提樹・・・と言うか、実玉の場合、種子を除いた殻部分を使うわけです。
ただ、殆どの実玉は、種子はそのまま残していることが多いので、ピーナッツのように美味しい中身は虫の大好物。
虫食いの要因になりやすいのです。
「虫食いが進むと、珠の中が中空になるから念珠を擦る音がよくなる」なんてことが昔はしたり顔で言われたものです。実際そういう側面もあるのです・・・が、現代人はなかなかそういう話では納得してくれませんし、したいとも思いません。
そこで防虫加工した玉が流通するようになるのですが、薬で防虫したものは使用したくありません。そこで通常、うちで防虫加工と言った場合は、玉の穴部分に糸通しのための中空のピンを差し込んだものを一玉一玉差し込んで加工したものを差します。
さらに上級な処理の場合は、っていうことで、この天竺菩提樹のように殻の部分だけを材料にして玉に磨るという方法が考えられるわけです。
解りやすく言えば、クルミを想像してください。
念珠に使う材料はその皮部分のようなものです。
あの殻の部分から玉を抜く。
と言うのは簡単ですが、とてつもなく不可能に近い作業なのです。
なぜなら・・・
10(14)mmの厚みの殻が必要であるからです。
クルミの殻なんていったい何ミリあるでしょう・・・
と言うことは、肉厚があり、きめが細かく、照りが良く、色合いが爽やか、そしてとてつもなく大きな実を厳選して製作するのです。
それを何十玉と均一なもので揃えるのですから、いかに大変かと言うことなのです。
で、出来上がったのがこの天竺菩提樹の片手念珠です。

一見しただけではわかりませんよね。
手で持っていただければ、中空の天竺菩提樹より玉が小さくとも、ずっしり重いことに気づくはずです。
念珠はおもしろい・・・
何にしようかな
人工虎目。
今は簡単に手に入るけど、十年ちょっと前は、なかなか難しかったんだよ。

もう一声
ちょっと結び部分物が足りなかったので、もう一結び付け加えることにしました。
少し豪華に見えますね。
これでほぐれの防止も兼ねるので、より組み紐部分が強くなります。
一石二鳥。


始めに付いていた房と比べると全体が引き締まりました。
華籠結び完成

感性間近

華籠結び最期の段階。
浅草のそら

夏の終わり
朝の情報番組を観ていた。
その中のあるコーナーで
「最近の子供たちの夏休みの宿題の進捗状況はどうなっているか」
をテーマにしていた。
まず驚いた。
子供たちの宿題の手際の良いことにである。
ドリルはほぼ完了している、作文類は5~70%、自由研究や日記類はさすがに日を重ねないとできないものは、しかし着実に手がけている。
すこぶるしっかりしている。
し、そういうシステムを学校側もとり始めている。
冷房完備の教室をもつ最近の学校設備の状況を考えると、いっそ夏休みなど廃止したらよかろうにと僕は考えてしまうのだが・・・
(お盆休みは伝統文化維持の為に残しておきたい)
番組のキャスターら大人たちの子供時代を振り返って同時期の状況を質問されると、0%と言う答えが半数を占めていた。
僕もご他聞にもれず、その大人たちの仲間に入る。
8月31日の夜は朝までかかって家族総出でなきながら突貫工事をした記憶もある。
着実にクリアーしていく現代の子供たちのしたたかさに驚きはする。
が、反面、塾や習い事にスケジュール闘争をし、友人みんなが集まれるのは夏休み中何回もないと答えた子供に、て炎天下のプールに毎日通う真っ黒になる子供の姿の少ないことに一抹の寂しさを感じたのは僕のみではなかったろうと、勝手に考えてしまった。
公園に行けば友人たちが炎天下の中であろうと、ランニング姿で真っ黒になった友人たちが遊びまわっていた光景が、いつでも目を閉じると思い浮かぶのだ。