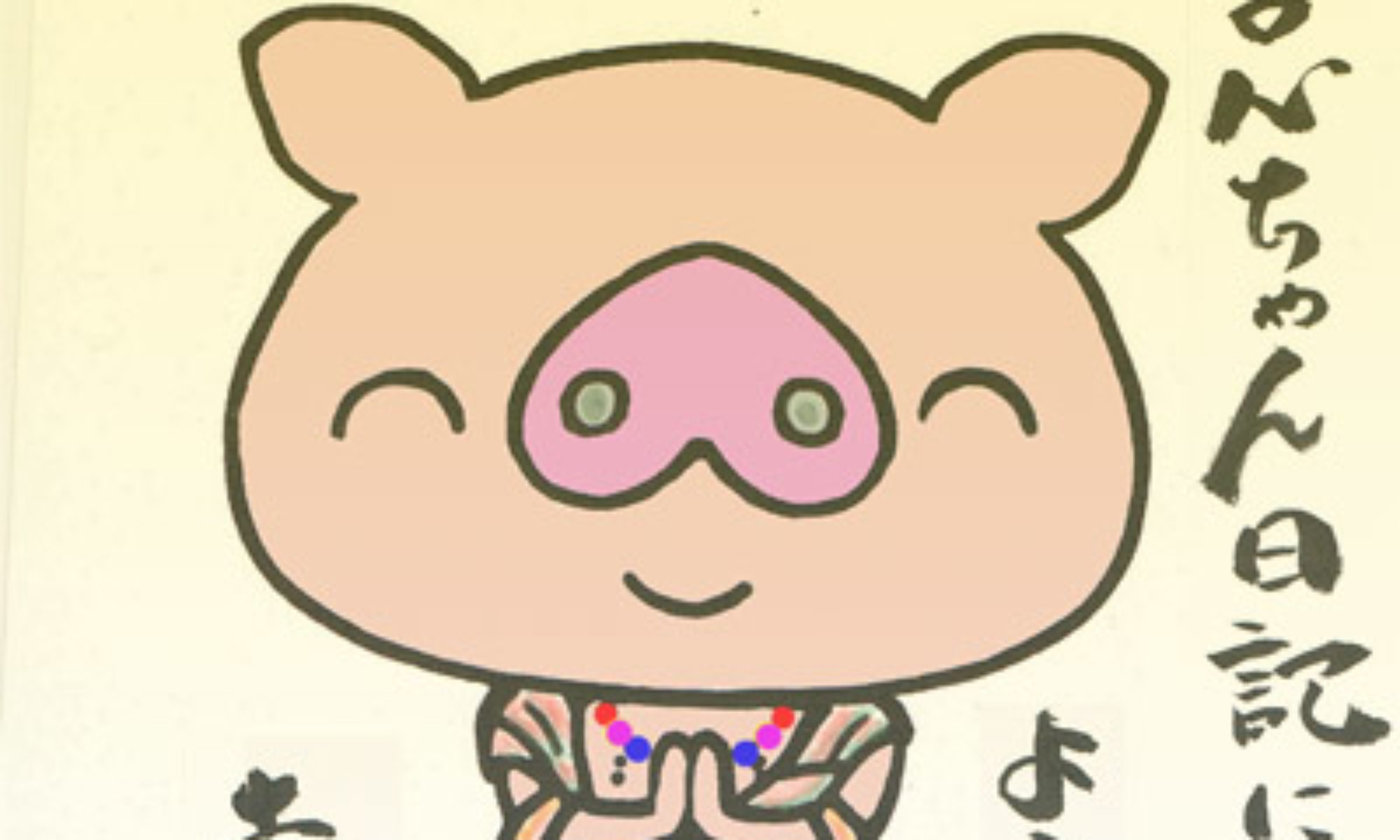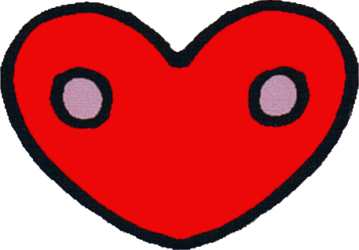金具師の香立

梅后流かっぽれ新年会
念珠堂の通り会、発足のときに、誕生祭を行った。
ちょうど三社祭り当日でもあった。
その際梅后流かっぽれの皆さんが百人踊りをして祝ってくださった。
実に嬉しかった。
一年たって、新春の初顔合わせに呼ばれた。
600人を越える全国からの師匠たちや招待客にビューホテルの会場もえらく狭く感じた。



詩吟や詠い、日舞の師匠方の集まりにも以前招待された事があったが、それぞれが何百人も門弟を引き連れている人たち。凄まじいオーラを感じて圧倒されたことを思い出した。
そのときとはちょっと違う感覚を覚えた。
伝統を背負う者にありがちな独特の弾き飛ばされそうな強さは感じるのだが、全体に調和があって心地よい。こんな空気を垣間見えたのは、梅后師を慕う求心力が師弟関係というより家族関係に近い空気だったためなのかも知れない。
中心に立つもののありようの違いで、会の雰囲気は全く異なるものだと教えてもらった。
浅草のそら

不動明王
価格にしては、すこぶる彫りがよい。

大きく見えるでしょ。
でも、実は小さい。のです。

楠の木が素材。
42000円です。
同じシリーズにはあと7体あります。
千手観音、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、勢至菩薩、大日如来、阿弥陀如来となります。
双身歓喜天

最後になりました。
朝から文化
いつものように朝は駒形橋から隅田川沿いをぐるっと一周してきた。
最近よく見かけるのは外人の観光客の姿。
一つはバックパッカーの姿。
一人ないし二人連れが多い。
近くに安い外人向けの宿が増えたのもその一助になっているのは明白なのだが,
それだけ浅草に何らかの魅力を感じて下さっているのだと解釈している。
今ひとつは、日本人ガイドの引率による少人数のグループ。
プロの通訳もいるだろうし、ボランティアも、はたまた企業の接待もいるだろう。
TON店長が気になるのは、引率の日本人の姿勢なのだ。
ひとっ走り終えると駒形堂の境内に戻ります。
駒形堂は、浅草寺に奉られる観音様が1400年の昔、隅田川、当時の浅草ノ浦から二人の漁師の網にかかり、陸に上がった重要な場所。
それゆえに近くは戦災、震災何度もの火事に見舞われながらも、再建され今に至っている、浅草寺にとっても重要なお堂。ついでに言えば浅草寺の戒殺の地でもある。
いつもここに到着すれば、何をおいても堂内の馬頭観音さまにお礼を言って手を合わせる。
と、背後に人の気配。
パチりパチりと写真を撮っている様子。
お礼も終って、境内に下る。振り向きざまにそのグループが外人のグループとわかった。
柔軟体操をしていると、一人の男性は手をポケットの突っ込んだまま鍵のかかった堂内を覗き込んでいる。
一人の女性はお堂に上がる階段でポーズをとっている。
5~6人の一人一人ものめずらしそうに階段を上がったり下ったり。
確かに西洋に住む人々には、こんなベンガラの堂なんて珍しくていかたないだろうから興味深々なのはわかる。
かといってそこが宗教施設である以上それなりの礼儀があることは、洋の東西を問うまでもなく同一なのだ。
そこがどういう場所かを理解しているとはとても思えない行動をとっている。
わからないならば、教えなければいけない。
教えなければ、他のどこへ行っても同じ孝道をとり続けるだろう。
それを、引率の日本人がコートに手を突っ込んだまま早く行こうとばかりに足を外に向けながらも静観している。
言えば良かったと後悔した。
あなたたちはキリストの家、つまり教会に入っても手をポケットに突っ込んだままなのですか?と。
宗教はその国の文化である。文化の中の文化である。
宗教の儀式から生活様式に変化したものは・・・というより、例えば日本の文化から仏教を除いたら言語としても、生活様式としてもいかばかりのものが残るだろうか。
仏教や神道が原点、つまり文化の種になってきたのである。
海外に足を運ぶものは、他国の文化を知るために海外旅行をしているのではないのだろうか。
(それはそのまま日本人の旅行者にも言えることなのだが)
他国の文化を理解せずして帰国するなかれ。というものである。
とすれば、その文化を教えるのは誰なのか。
そこに住む我々ももちろんそうなのだが、引率する旅行社、ガイドの人が宗教音痴ではこまるのである。
参勤交代の列を前に馬上で見物して、薩摩藩士に切り捨られた生麦事件も元はと言えば他国の文化への無知から来たもの。
今の世の中切り捨てるわけには行かないが、他国の文化、否、自国の文化のベースを実地で教えない引率は害をもたらすと言っても過言ではない。と思うのである。
日本人が日本人の文化を大事にする姿を美しいと感じた幕末の外人達の驚嘆を何かの本に書いてあったことを思い出した。
そこから汲み取ることは、今の日本人が日本を、日本の文化を守ってきた先人たちの遺徳に感謝する姿があれば、外人は日本の神様を前にしておいそれと覗き込んだり、ましてやポケットに手を突っ込んだまま見物する姿にはならないだろうと思うのである。
いよいよ