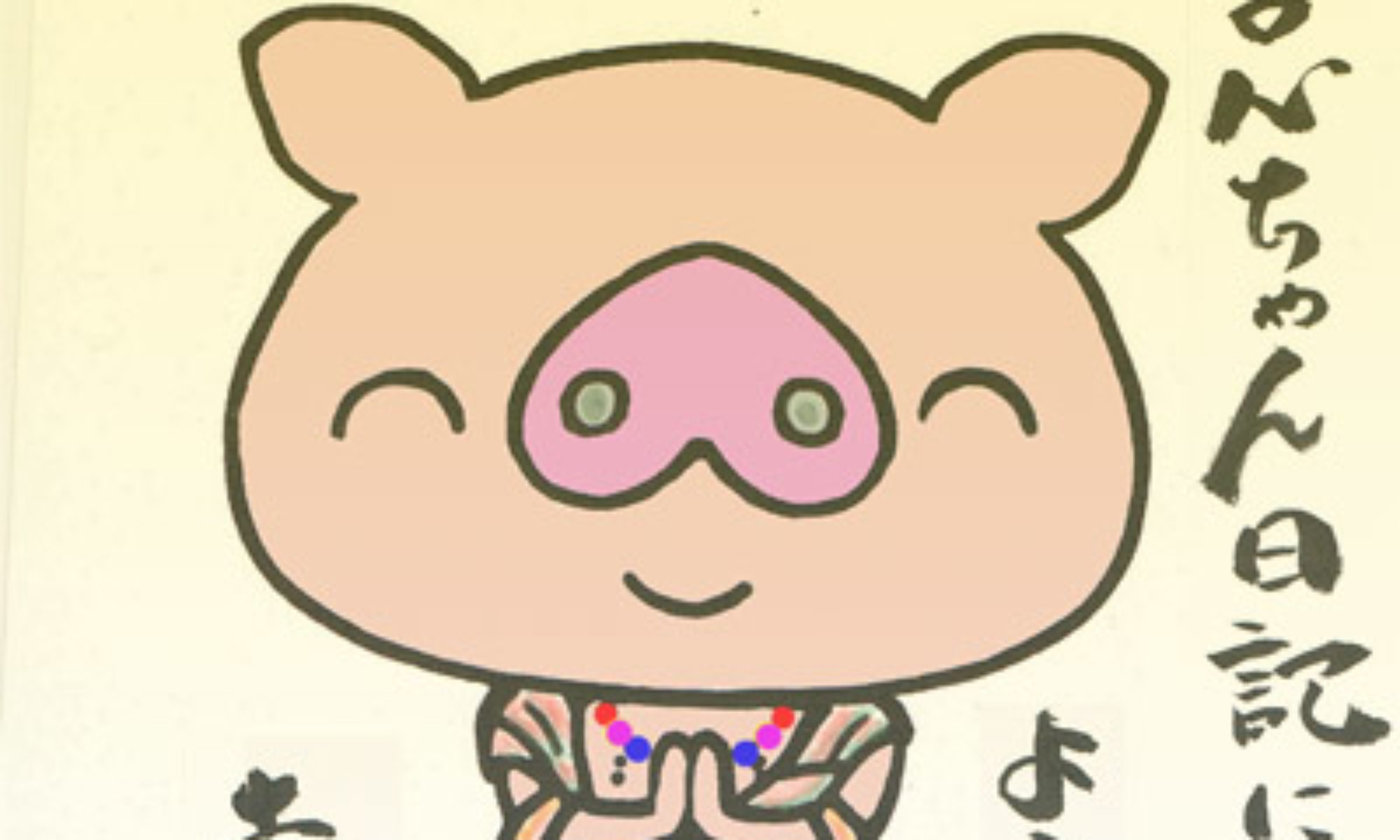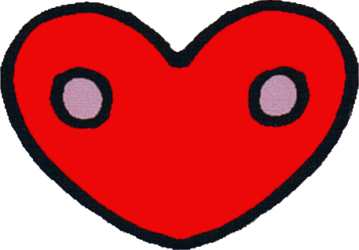「あたしが死んだらこれがいいわ。頼むわね」
大正生まれのちゃきちゃき江戸っ子姉さん。
○○さんとは呼ばないで、いつも「お姉さん」と呼んでいた。
ご両親を思春期の頃に亡くしながらも幼い兄弟のために懸命に生きられた。
歳を重ね体の自由が利かぬようになってからも、毎月の浅草寺へのお参りは欠かさなかった。
そのたびに、うさぎやのドラ焼を手土産に持ってきてくれた。
あるとき「お姉さんの若いときの写真が見たいな」と言ったことがある。
次の月、おずおずと恥ずかしそうに二枚の写真を手渡された。
そこには丸髷のかわいい少女が写っていた。
兄弟をかかえて生活していた少女は大人びて見えた。
目の前でお話ししてくれているお姉さんは同じ人なのだ。
生命の・・・いや、
人生の、不思議さが不意に脳裏を駆けた。
若い人から見れば一方の大人であっても、心はなんら変わることはないのだ。
自分は老人とまではいかないが、死ぬ時まで気持ちは変わるわけではないんじゃないのだろうか・・・
時という不変の法則下にある肉体の変化はどうにも手がつけられずとも、心の風景は故郷にいる親元にいつもある幼少の自分なのだ。
「彼岸に行ったら、お母さんに弟のことを守ってきたよと報告できるようにしたいの」
その思いは遂げられただろう。きっと。
その人のお位牌をお作りする時がいよいよきた。