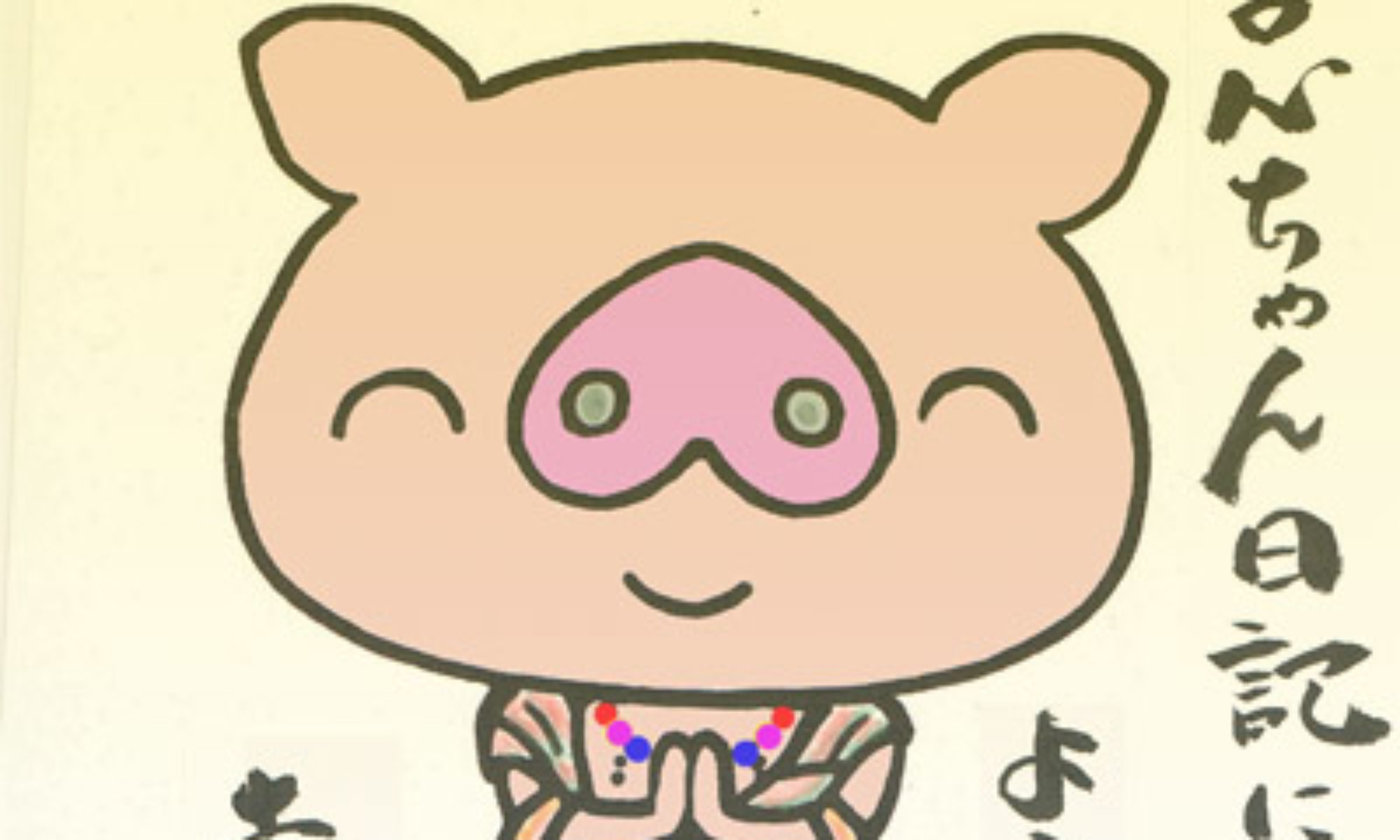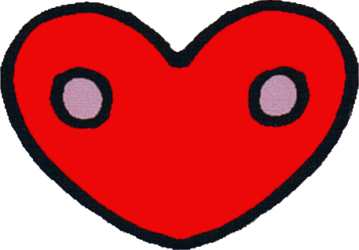お針箱の小さいものを想像して欲しい。
お針箱なんて言葉は死語かもしれないから、玉手箱みたいなもののほうが解りやすいだろうか、身と蓋都に分かれるケースだ。上からかぶせる箱のことを言いたいのだが・・・
その小さな玉手箱を真鍮の板二枚を使って上下の蓋部分と身を金づちで叩きながら成形する。出来上がったものは、蓋を身に乗せると音もなくゆっくりスーと滑るように落ちる。上等な桐ダンスの引き出しを閉める時のようななめらかさで。
これは0.1ミリの誤差でもスムーズに蓋は落ちない。
今時ならば、金型をつくりプレス機械であっという間に製作するだろうが・・・
一見すればどうということのない検便の容器のようなものなのに。
しかしこれは職人の技術をすたれさせないという僕らの仏具業界の使命のような仕事としてとらえられて作り続けられている。
最近、京都の職人と話す機会があった。
四分一という、銀と銅の合金を用いて密教の法具を製作する技術がある。
仕上がりにかける色合いがなんとも言えないもので好きな法具のひとつなのだ。

どんな小さなピンホールも一切許さない加工技術がないと理想の仕上げができなくなる。
とても難しい技術であることはわかっていたが、高額なものなので、数点しか店に在庫していなかった、というかできなかった。(^^;;
その最後の一点をはいてしまったので、再入荷しようと思ったのだが、帰ってきた答えは・・・
「もうできない」
だった。
「え!うそでしょ」
正直戸惑った。
「西海さんだめなんよ。高齢化でね・・・」
彼も素材がなければ何もできないわけで、それこそあがったりになってしまう。
必死になって素材を作れる職人を血眼になって捜している最中だった。
じつはこんなことが最近連続している。
無駄と思われることであっても、後世に残す技術と伝統を保持していかねばならない。
改めて足元に火がついていることに気付かされた。