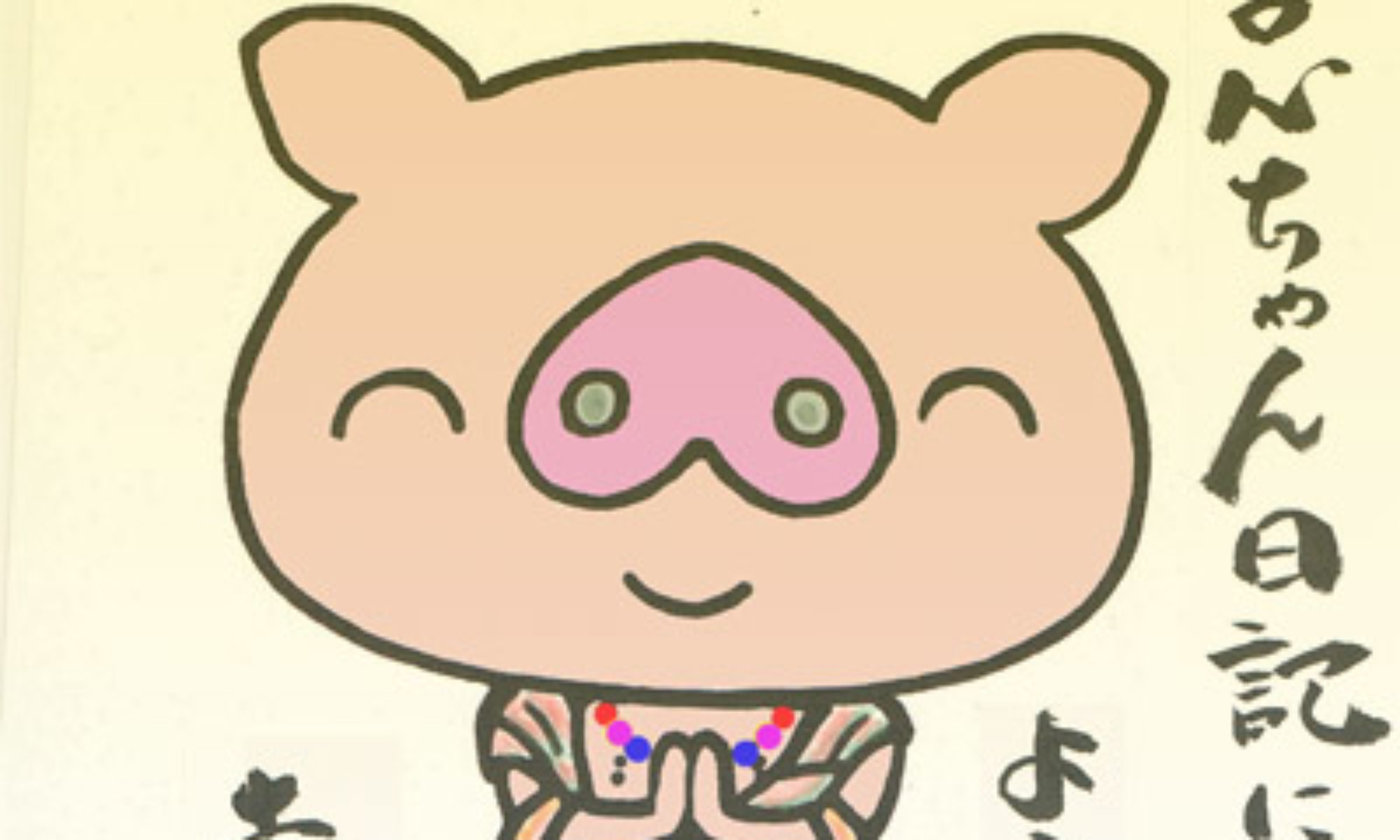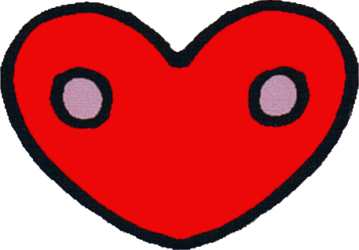秋の彼岸になると決まって子供の頃の墓参りを思い出す。
TONの父親はTONが3歳の時に亡くなった。
押しかけ女房だったという母を肯定的には取れなかった父の実家とはほぼ疎遠状態だったのだが、こと人の生き死にの問題となれば、一肌脱いでくれるのではとの母の予想を裏切るかたちとなった。
遺骨をどこに収めるかその場所がない。
著名な大学を主席で卒業した前途有望だった夢多き父の死に様は人からの借金には快く応じない銭まで調達して出したおかげで文字通り無一文状態であった。すべてを母が肩代わりしていたという有様で、葬儀を終えた時には500円札一枚が一家の全てであった。
もちろん墓など買う余裕どころか、明日からどう暮らして良いか途方にくれた。
下げたくない頭を下げに実家に出向いた。嫌味の数々を受け流しながら父の遺骨は本家のカロウトーの片隅に預けられる形となった。結局そこが13回忌を迎えるまで菩提を弔う安着の場所となったのである。父としては肩身の狭い思いをしただろう。母の口癖だった。それは同時に、実家への複雑な思いを代弁する母の想いの言葉だったと今では思う。
春の彼岸、秋の彼岸と田無にある父の実家への墓参りが始まった。
TONが覚えているのは5歳のこと。二つ上の姉に手を引かれその姉の手を母が引き、まだ西武線が高田馬場を始発にしていた頃であり、山手線に乗り換える必要があり、渋谷駅の迷路の中を右往左往していた母の心細さが電信のようにTONの心にも伝わった。
あとは断片的にしか覚えていない。
ただ、当時生活の足となっていた東横線とははるかに垢抜けせず田舎の電車だったこと。
風景も田舎の風景の中をとろとろ走っていたこと。目的の花小金井の手前の駅で時間調整のため長く待たされていた記憶。ホームから改札へは駅内踏切があったこと、墓前の花を買った駅裏の花屋がなんとも田舎臭かったこと。駅前は未舗装のまま、雨の日の墓参りの時は足元に難渋した、などなど、なんとも田舎に来たなぁと子供心の印象だった。
父の学生時代は一山越えて出かけると、たぬきが出てきて先導してくれたという話があながちでたらめではなかったんだなぁと十分納得できる環境だった。
はじめの一、二年の母の付き添いも、そのうちお前たちで行っておいでとなる。それこそ大海原を羅針盤一つで大航海した船乗りの心情だ。。。
今思えば居候の立場でしかない父の墓参をするたびに母の思いはいかばかりだっただろうか。それが理解できるまでは数年要した。TONにとってのお彼岸の墓参は父への供養もあるけれど、母の心情のトレースでもあるのかもしれない。
秋のお彼岸を迎えると、川辺に咲いてた彼岸花の赤色と田無の駅の待ち時間、突き抜けた青い空に遥か高所をトンビがのんびり円を描いていたのんびりした風景が脳裏に浮かんでくるのだ。