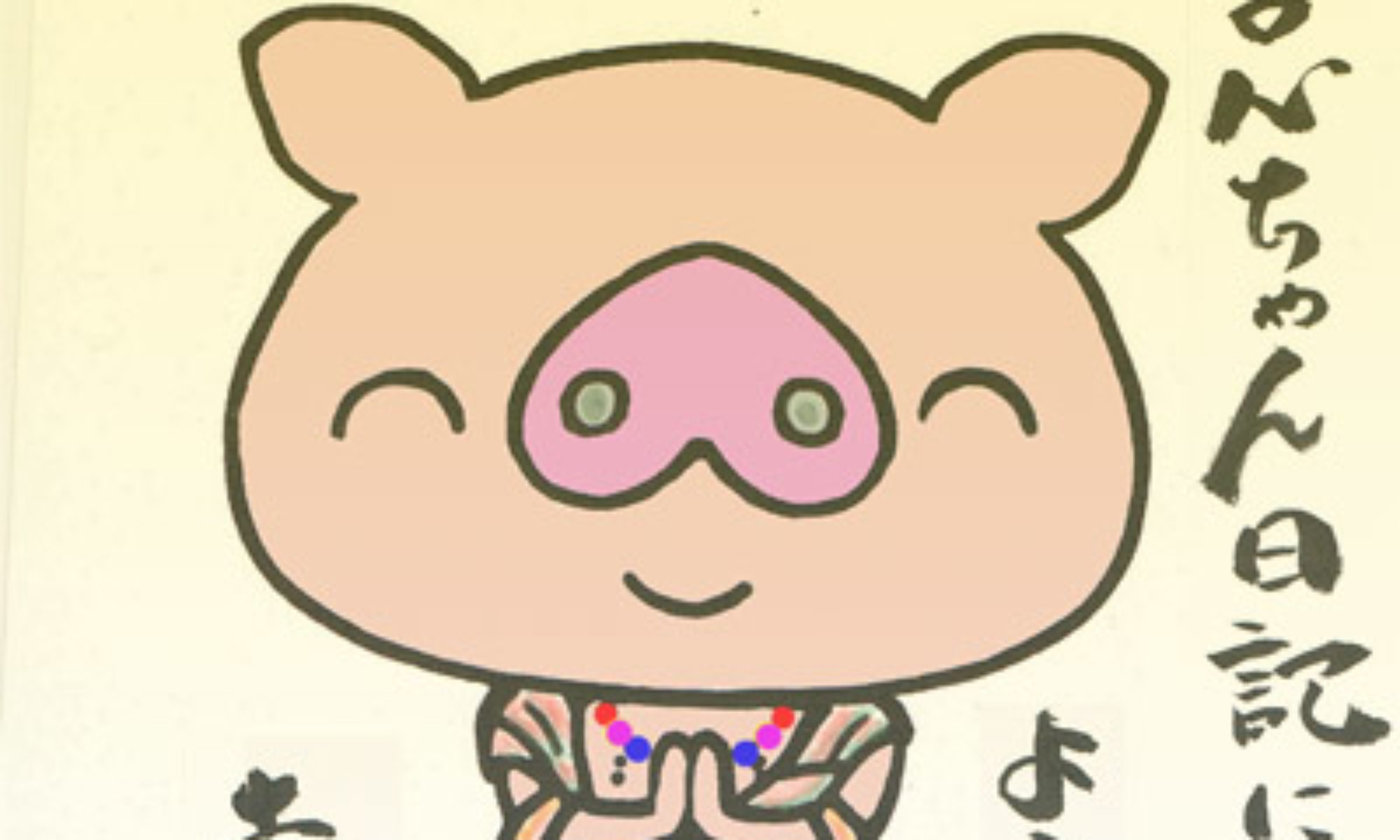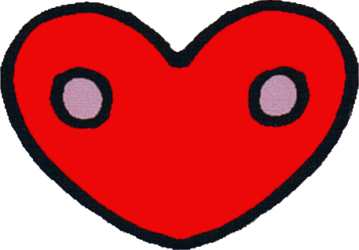代書を頼まれた。
遠野生まれのKさんは、20年来のお客さまになるのだが、お付き合いの長さではなく、頼まれればいやといえない僕は、あっさりと引き受けた。
四捨五入すれば九十の齢に達してしまう彼女であるが、今もはつらつと整体の仕事で東京中を駆け回っている。
150cmにも満たない小さな体ながら、過去に大男を投げ飛ばした武勇伝もある。
日本で整体の草分け的存在の彼女は他所では先生と呼ばれるのに、僕とお話しするときは、一田舎生まれの長生きの少女に見える。
研究熱心で、いまだに解剖学の研究や、新カルチャーの習得に余念がない。
良いといわれる書物は通読を欠かさないし、しかも眼鏡もかけない。
でも、書き物は僕に手伝ってと、いつもそっと依頼される。
そんな彼女がたどたどしい字で書いたはがきを見せてくれた。
義理の弟が亡くなったのでお線香と一緒に送りたいけど浄書してちょうだいというのだ。
はがきを差し出された。
一晩かけて書いたのだという。
(はがき一枚を?)
クエスチョンが心の中で湧いた。
亡くなられた義理の弟は大戦中、中国に出征した。
戦後三年半のシベリア抑留され、帰国した時には結核を患っていた。
彼は、結婚式も挙げぬまま、顔を見ることもなく出征し戦死した婚約者の弟に当たる。
つまり彼女は初めの夫となる人物と結婚式もまともに顔すら見ずに逝ってしまったのだ。
添い遂げられなかった兄の無念を思えば家族としてまた、当時のしきたりからもその弟が結婚相手に選ばれるのが常套だった。
しかも彼は、親戚関係にある兄弟の仲でもよく知る青年であった。
しかし彼は、自分が結核にかかったことを知り涙ながらに身を引いた。
彼女の知らぬうちに。
彼はその後、療養生活に入り、病を克服し、他の人と結婚した。
そこまで話をすると90に手が届かん齢いの少女は、涙を流した。
60年をはるかに経過した昔話ながら、彼女の心では「今」なのである。
お悔やみのはがきを書こうにも、一文字書いては涙を落とし、一文字書いては、当時を思い出し、そして泣き明かし、たった八行のはがきを書くのに、一晩かかってしまった。
はがきの文字の行間には現しつくせない、心のバックヤードがついて離れないのである。
吹けば飛ぶよな一枚のはがきなれど、なんと思いはがきなのだろうか・・・
僕も涙があふれ出た。
「この一行は10年ですね」
僕が口を滑らすと、
彼女はまた、目頭を押さえてしまった。
<<前の日記へ