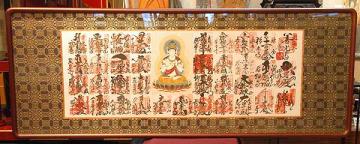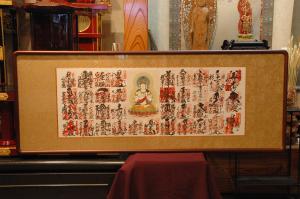最近、2社から取材を受けた。
一社は業界誌、もう一社はメジャー誌
今までも、媒体は様々だったけれど、
何度か取材していただいてきた。
おもしろいことに、質問は、だいたい同じ内容
そして、同じリアクションになることが多かった。
今でこそ歳相応の顔になったけれど、
30代や40代の頃は、業界的には、歳が若かった。
(もともと若く見られがちではあるのだが・・・)
それが責任者をやっているのだから、
仏壇屋の跡継ぎと思われてもしょうがない。
見るからに極楽とんぼだったことは言うまでもないが…
「代々こういうご商売をされてきたのですか?」
だいたい、この質問から入る。
僕が元エンジニアであり、仕事に誇りもあったし、
心から愛していた。
反面、絶対やりたくなかったのが商人だったと話すと
ほぼ、身を乗り出してこられた。
なんで畑違いの業界で起業したのか?
しかも70軒も群雄割拠している浅草に。
十中八九そんな質問になる。
「僕が学生時代からの親友を自殺で失って、
それまでの価値観が音を立てて崩れちゃったんですよ。
そのときが人生を見直すきっかけになった」
と応えると、同情はできるけど、
仕事を替える理由にはならないのでは?
とでも言いたそうな…
何ともいえぬ空気が、その場を漂う。
キョトンとしながらも、何となく納得してくれる。
そんなものかなと言う顔に変わる。
そんなバかもいるのかと思ったのかもしれないし
あくまで取材だと割り切っちゃうのかもしれない。
それとも、そんな方程式を誰もが心に持っているのかもしれない。
でも事実、自分でも不思議なのだけれど
本当にそう思っていまったのだから仕方ない…
理想の足が外れたとき、人はどう対処するのだろう
どう思い、どう動くのだろうか。
興味がある。
当時、妻や子供への責任が伴っていたら、
たぶんこの仕事への縁は生まれなかっただろう。
あらゆる縁が重なり合って今に至る縁が生まれた。
死ぬほどの心の痛みを持ちながら、
相談に乗ってやれなかったトラウマは、
ある時期まで、この仕事への原動力になっていたと言える。