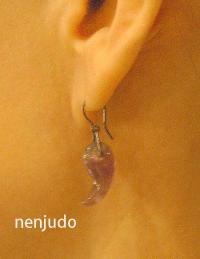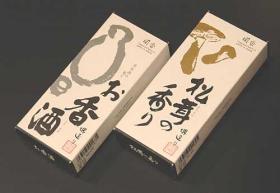晴れた、晴れた。
案の定、晴れた。
もう…これだけ春を感じる陽気に誘われたんじゃあ
誰でも、外を闊歩したくなるってえもんでしょう。

ただし
僕は浅草からは出られません。

頑張んなきゃあね。
80歳を越えられた、おばあちゃん先生がご来店された。
おばあちゃんなんて言葉は、本当はふさわしくない。
背は人一倍小さいけれど、人の二倍足が速い。
カイロの先生。
もう十年を越えるお付き合いをしてくださっている。
四国に出かけられる準備。
その場で杖に戒名を書き、持ち物にお名前をお入れする。
するとニコニコうれしそう。
この笑顔につい力がでてしまうんだなあ。
お礼にと、足のマッサージ。
どうぞ
気をつけてお出かけくださいね。