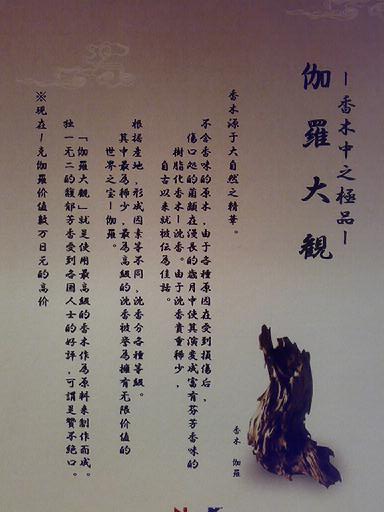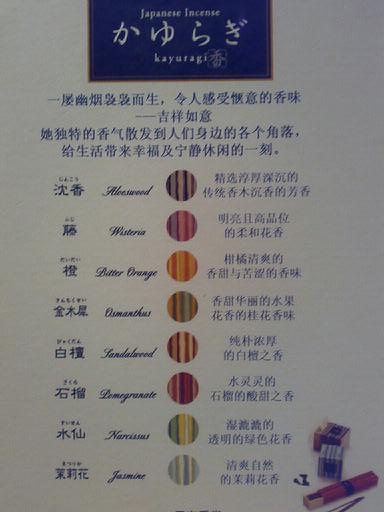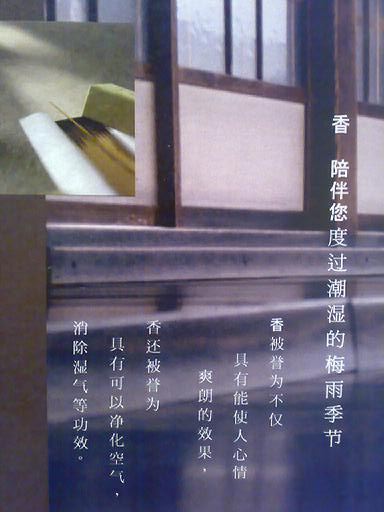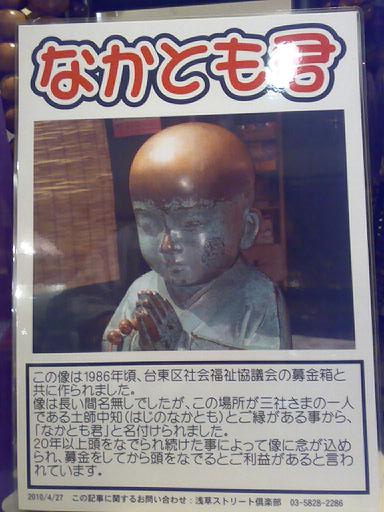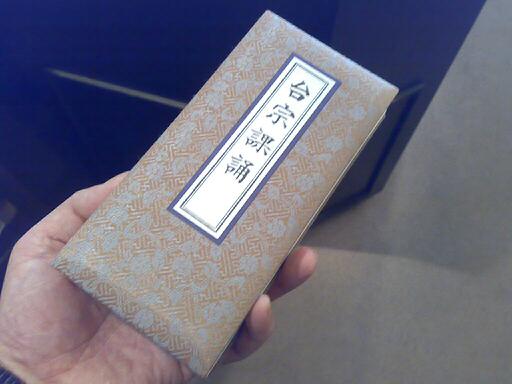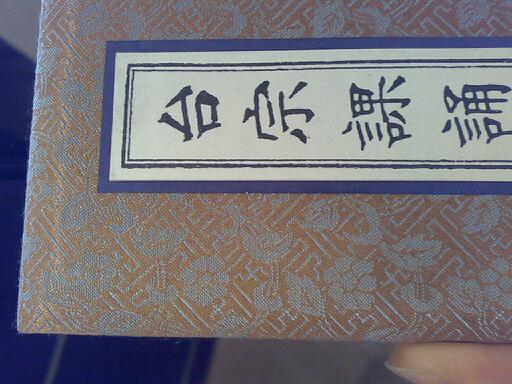「この絵はどなたが描かれたのですか?」
店の奥で今日出荷予定にしていた念珠の最終仕上げをしていた背後からふと声をかけられた。
難波画伯の観音菩薩の絵をさして質問されたのだ。
この絵はずっと昔に、画伯が存命のころ気に入っていただいたものだった。
ご本人はクリスチャンであり抽象油彩画家ながら、死線を越え仏教に傾注していく中で一宗一派を引けるほどの器を持つ方だったが、惜しくも60の坂に入られて間もなく、惜しくも逝かれてしまった。画伯の絵に共感をもたれたお客様は多いが、今日は一味違った。
お尋ねいただいた方はある日突然観音様がご自分に顕れたと言う。
その観音様を絵になさっているという。
ちょうどお手持ちの絵があったので拝見させていただいた。
なんとかわいいのだろうか・・・
儀軌や仏教画を学んだわけでもない。
お会いした観音様を得になさっているのだという。
最近は、そこに聞こえる旋律を楽譜にあらわし、CDに吹き込んだと貴重な一枚を頂戴した。
こういうことを不思議なこともあるものだと人はいうのかもしれない。
でも僕は当たり前なことのように自然なこととしていつもながら受け止める。
さもありなん。
その方に何かのお役があるんだろう。
科学で説明できないことなんていくらでもある。
むしろ科学がまだ幼稚なだけだと思ってるから。
茶化しちゃいけない。
もうずっと以前、讃祷歌(さんとうか)を世に出した真言宗の僧侶、新堀智朝師に親しくしていただいたことがあった。
師は音符を読み書きすることはできなかった(否、この表現は正しくなかった。始めのうちはであった)。
ある日、子供が使うような大きな五線譜に耳の奥で響く旋律をやっとの思いで書き留めてみた。
わずか数小節の譜面が完成した。
人伝えに音大出のプロの作曲家を紹介してもらい、恐る恐るその譜面を見てもらう機会を得た。
プロの音楽家に見てもらうにはあまりにも幼稚すぎる譜面。
案の定けんもほろろに鼻であしらわれた。
作曲家はせっかく尋ねてきたのだからと、音符を目で追ってみた。
次の瞬間、眼の色が変わった。
生前、住職が僕にもらした。独り言のように。
「くやしいのよ。もっと早くに気がついていれば」ちなみに住職は尼僧である。
「讃祷歌を十年早く世に出したかった。そして現代に問いたかった」
と。仏教歌の枠を超えた讃祷歌はローマ法王の国連の会議室にまで招聘された。
若い頃から耳の底では、こぼれるように旋律は吹き出していたという。
けれど、多くの曲を鼻歌で終らせてしまった。
定期公演を最期に惜しまれながら彼岸の人となってしまった。
だれも天賦の才がある。
それが何かは、またいつ発芽するかも解らない。
素直にその内なる声を受け止めてみてはどうなのだろうかと思う。
自分のことが一番わからない・・・