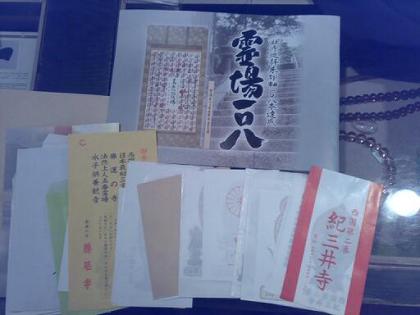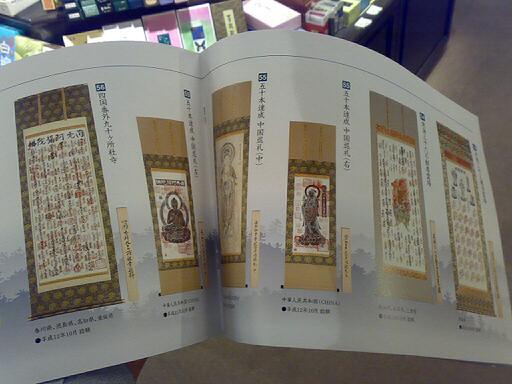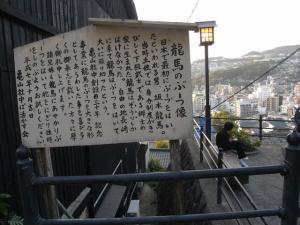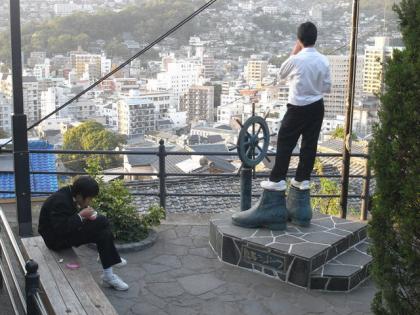同行二人
元々は四国遍路に向かう巡礼者に対して、お遍路は一人で巡るのではない。常にお大師さまと二人なのだとする宗教的観点の理解からくるものなのだ。
だからこそ、四国に入る前にわざわざ遠回り(でもないけれど今は・・・)して高野山奥之院に今なお禅定されているお大師さまをお迎えに行き、八十八ヶ所巡り終えれば、もう一度、奥の院に戻りお戻りいただくのだ。
午前中に店に来られた強持ての紳士は、「また来るね」と手打ちの大徳寺を置き去りにして店を後にした。
夕方再び戻ってこられた時、僕は手作業の最中でお相手できず、代わりに相棒がお相手させていただいていた。
10万を越える手打ちりんと朱の厨子を求めてくださった。
朱の厨子に何かを入れているのがチラッと視界に入った。
「窮屈だなもう少し大きいの」と注文をつけた時、初めてその人が午前中の紳士であるのに気が付いた。
倉庫から一回り大きい厨子をお見せした。
「ん!これならいい」
よく見ると、位牌だった。
「今度一緒に旅するから」
輪島塗をさせたという位牌は、きれいなつやを見せていた。
梱包をするために暫し時間が空いたのを見計らって手を休め、朝のお礼を言った。
ついでに、旅することの意味を聞いてみた。
紳士は長く海外生活をされていた。妻に癌の兆候が見られて闘病のために一時帰国した。帰らぬ人となった。
自らも同じ病を発見し闘った。
幸い発見が早く川を渡ることはなかった。しかし妻は渡ってしまったんだという。
先ほどの美しい位牌を愛おしくさする様が脳裏に浮かんだ。
「だから一緒に旅をする」
そうですね。
いつかあちらで逢えますね。
「いや。まだだ」
遣り残しの仕事が山とあるのだろう。
「また海外に戻る」という。
奥様とともに・・・
長く居た海外には最愛の人の余韻が残っているのだろう・・・し。
夫婦は同行二人。