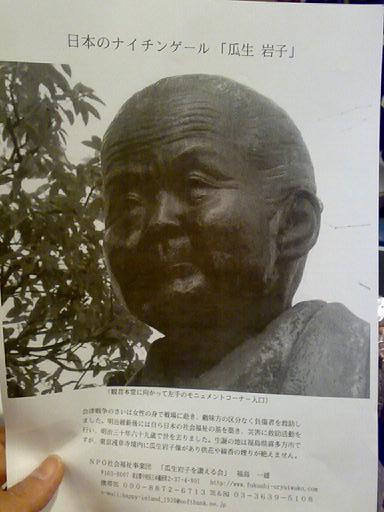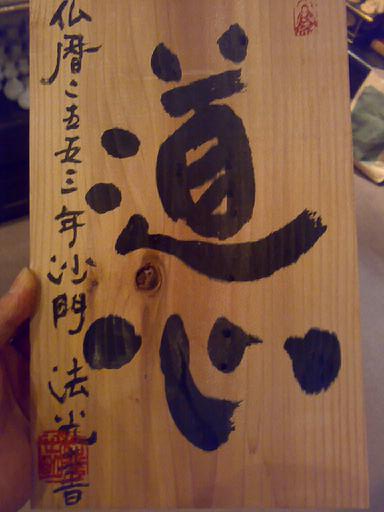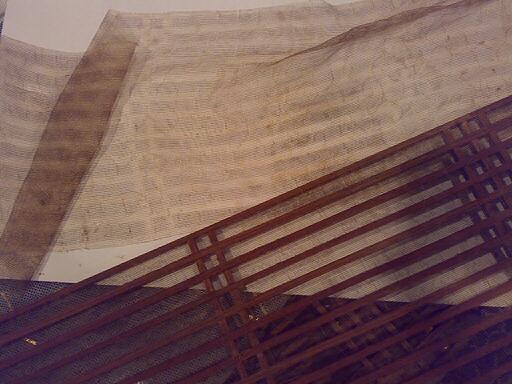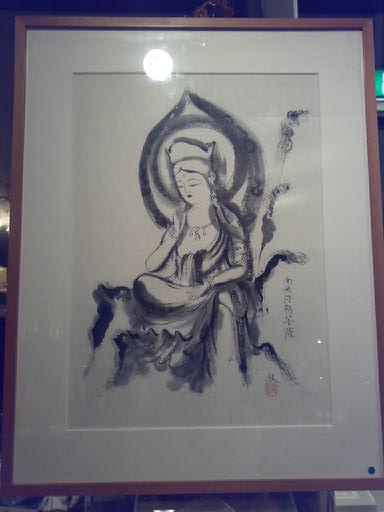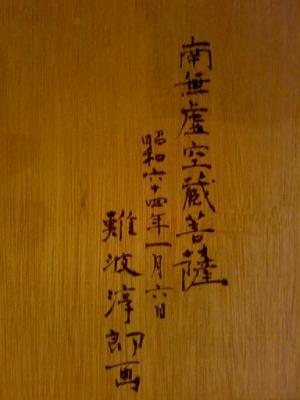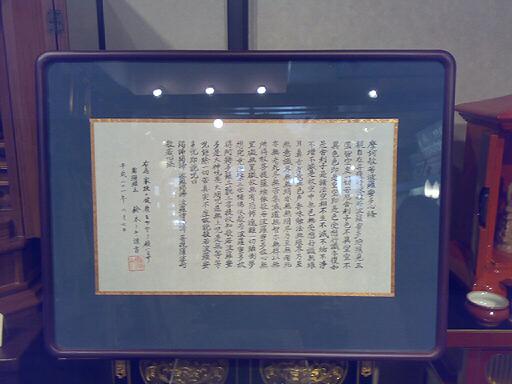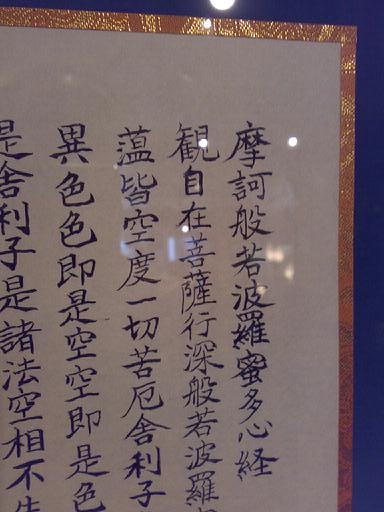念珠のお直しを承った。
先代から伝わった念珠と言うことで、そうと年季が入っていた。
むくろじゅの素朴なスタイルだった。
これは何ですか?と尋ねられるので、お釈迦様と円の深い実ですとお答えした。
マガダ国が他国から攻められたとき、国民が一心にむくろじゅで作った念珠で念じなさいと言われた逸話のことであった。
しっかりメモをとられ、大事なものだったのかと再認識してくださったようだった。
「制作期間はどれくらいかかりますか?」
と再度聞かれるので、
2週間くらいと応えたけったけれどちょっと混んでいるからなあと心に湧いてきて即答しかねたとき、「何かご使用になることがおありですか?」と尋ね返してみた。
「はい。妻が一週間後に他界するもので・・・」
末期がんだった。
以前、がん患者の集いに毎週通っていた頃のことが頭に浮んだ。
痛みに対して、モルヒネを打てばよいのだけれど、当時はなかなか打ってはくれなかった。もちろん患者の体を考慮しての病院側の判断だったのだろうけれど、患者も看取る家族もせめて痛みだけは・・・終末医療の現場のものすごさを聞かされていたことを、ふと口にした。
「今は痛みだけはとってくれるみたいだけど、ご家族の気持ちは複雑ですね。」
一瞬、お客様の顔がパーッと明るくなるのがわかった。
きっと今まで深刻さに蓋をしてこられたのだろう・・・
危うく目から汗をこぼす所だった。
かろうじて鼻からのどに送り込んだ。
自分ならどうだろう・・・
いつか看取る側になるか、看取られる側になるかわからないけれど。