どうしてこんなにと思うほど
砕けているという言葉のほうがふさわしいちぎれよう。

正絹の糸で中通しされた念珠。
もちろん古いものだろうし、昔は余糸を撚って通す場合もあった。
擦れにさらされると、堪らない。
なあんだ

予想外
と言うか、やっぱりと言うか。
糸が通らない。

日本人
読売新聞の5月30日版をリサイクルゴミとして
束ねてあった古新聞の山の中からようやく引っ張り出した。
というのも、先日、横浜のO氏の来店の際、
「日本人の宗教観」の調査結果面白いですよ
とのお話しを受け、興味をそそられたからに他ならない。
老眼鏡をかけても見え辛い目をこすりながら
隅から隅まで読みふけっている間にガイアの夜明けを見損なってしまった。
それほど興味のある調査結果だった。
全国の3000人を対象にした調査で79年から定期的に行っているようだ。
いくつか例を上げると
<宗教を信じているか>の問いに
信じる 26%
信じない 72%
で、79年の信じる34%からは意識が後退している。
<幸せな生活を送る上で宗教を大切だと思うか>
思う 37%
思わない59%
79年には思うが46%だったからこちらも低下している。
お宮参りや七五三を神式に結婚式をキリスト式に葬式を仏教式に代表されるような
日本人には独特の宗教観があると思うが。
それを現しているのが、
<先祖を敬う気持ちをもっているか>
持っている 94%
持っていない 5%
縦の糸が切れていないことにホッとする。
<自然の中に人間の力を超えた何かを感じることがあるか>
ある 56%
ない 39%
漠然と見えてしまうが、とても大事なことだと思う。
<宗教団体について感じること>
どういう活動をしているかわからない 47%
人の不安をあおる強引な布教をする 43%
高額なお布施寄付を集めている 36%
98年と同じ上位3項目だったと言うのも面白い。
僕の経験でも、浅草寺をどこかの団体が勝手に占拠して、一般人がお参りすらできない状態があったり、白装束の団体が店前を手を繋いで顔を隠してぞろぞろ歩く、なんていう全くわけのわからない団体もあり、大教団にしても寄らば来いの姿勢では敷居が高すぎる。
そうでないと申しわけされたとしても、3万人の自死に対して宗教者は、少なくとも結果に責任を感じるべきだと思っている。
広報がもっともっと必要だよね。
<死んだらどうなるか>の問いにも
生まれ変わる29%
別の世界に行く23%
消滅する17%
墓にいる 9%
何らかの形で霊魂の存在に52%の人が同調している。
日本人の根底の宗教心はそうやすやすと崩れてはいないなあという感じがした。
が、同時に特定宗教には一線を引く感じも否めない。
これをどう見るかはとても大事なファクターだなと感じた。
真言宗の正梅水晶仕立

ほら
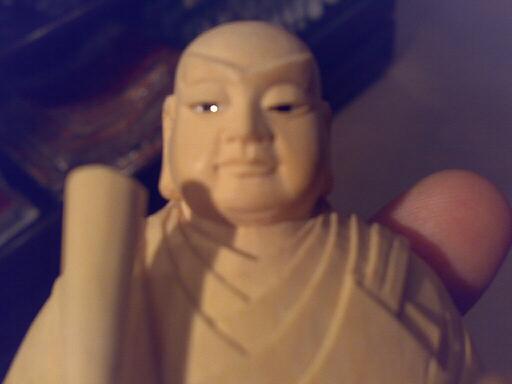
眼が違う
日蓮さんの柘彫りだが、眼に玉(ぎょく)をいれている。
ここまでできるか!驚き。

今日の浅草のそら

若さ、ばかさ?、柔軟さ
秩父霊場を廻る準備は完了し、
あとは天候次第となってから、
江戸時代の川止めを受けている旅人の気持ちだ。
仕事のけりがついて、出かけやすい状況になると、
決まって雨が降る。
というパターンがここ2週間続いている。
梅雨入りを恐れて、その前にと思っていたのに・・・
その恐れがはるかに早かった。
昨日から梅雨入りとなってしまった。
重い空を見ながらフッと考えた。
若い時ならどうしているだろう。
まず躊躇などしていないだろう。だいぶ違う。
後先を考えず、まず走り出しているだろう。
それなりの準備をしていたときもあるが、
雨具も持たず、ライトも持たず、
ましてや天気予報など見る気もしなかった。
予定したら、必ず実行である。
現場で雨に祟られることがあっても
それを受け入れてしまっていたに違いない。
信州の野麦峠を目指したときも、
伊勢志摩を巡ったときも、
妻籠に行ったときも、
冨士の頂上に自転車を担ぎ上げたときも・・・

(富士山頂上から30mほど下ったところ。やはり雨だった。)
結果、全て大雪か雨に祟られて大変な思いをしている。
けれど、なあにも考えなかった。
ましてや後悔などあろうはずはなかった。
濡れるのがいやだななども、これっぽっちも考えなかった。
結果、雨に降られて全身濡れ鼠になったとしても、
全天候が楽しかった。
「これも全て善し」だった。
考えれば相当無謀なことをしたと思うのだが、
そこが若さという柔軟さなのだろうか・・・
いやいや、なんのなんの、まだまだ・・・
今日の浅草のそら


