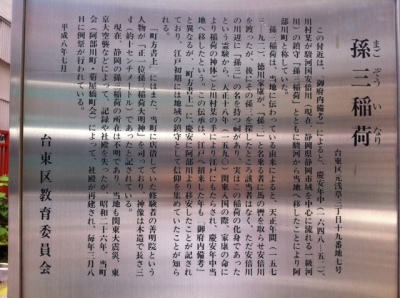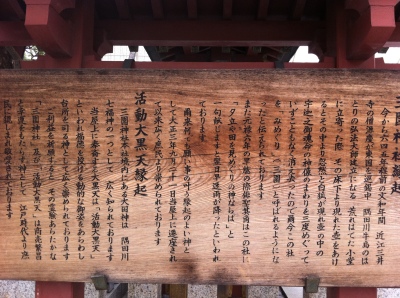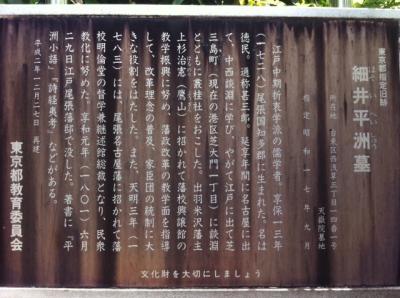東京藝大の芸術家の卵たちによる作品が今朝、浅草神社に搬入された。
「五右衛門」と命名されたビックキャットは、丸の内賞を受賞するほどの力作。
150匹以上の等身大の猫が寄り集まって・・・・言葉を変えれば、こころをあわせることで大猫となったのだ。
数十名の学生たち一人ひとりが、愛猫を思い、亡き飼い猫を思い、想い出の一こまを思いながらの心の集合体なのだった。
一匹一匹は力もない小動物でも、150匹も集まれば、こんなパワーを出すよとばかりの大形相を呈しているのだが、その目は鈴(鈴も魔除けを表す)大口を開ける逸れも猫、飛び掛らんばかりの前足も猫たちの結束した態。
一つになることで、大きな力を発揮できる何かを「五右衛門」は顕しているのではないだろうかと思うTONなのであります。
そんな暗示的な猫たちも・・・・
残念ながら作品の性格上、ねこちゃんは大学の保管時期を過ぎれば解体の運命にあった。
殺処分を忍びなく学生たちは里親募集の声あげていた。
・・・聞きつけたのが、念珠堂の参加する一之宮商店会ということなのだ。
雷門一之宮商店会自体、3.11の大地震以降いてもたってもおられず、被災応援ののろしを上げてきたことは、何度かこのブログで触れさせていただいてきた。
「心ひとつに」が一貫した合言葉だったし、支援をさせてもらううちに、ますますその言葉が必要な一点であることに深く気づかされてきた。
そんなわけで、学生たちの「心ひとつに」の象徴「五右衛門」に縁を持たせてもらった。と言うわけである。
朝8時、東京藝大前は、別れを名残惜しい?学生たちが見送りました。
きしくも藝大美術館では、明日から被災地支援の展覧会が始まる告知がされていました。
猫が猫だけに、搬入の難しいことこのうえなし。
馬道通りに大型トレーラーを置いて、雷門一之宮商店会メンバー、東京藝大のメンバー、仕事をしてもらう頭たち、総合力で搬入します。
もともと神輿の形なので担ぎ棒の上に乗っているのですが・・・・
重いはずなのだけれど、みんなニコニコしてますね・・・・

新門の頭も正装して来てくれていました。
今日は、仮置きゆえに雨養生をしてっと・・・
学生たちのリーダーが頑張ってます。

新門の若い衆、アメリカ生まれの自転車の薀蓄なかなかのものだね。