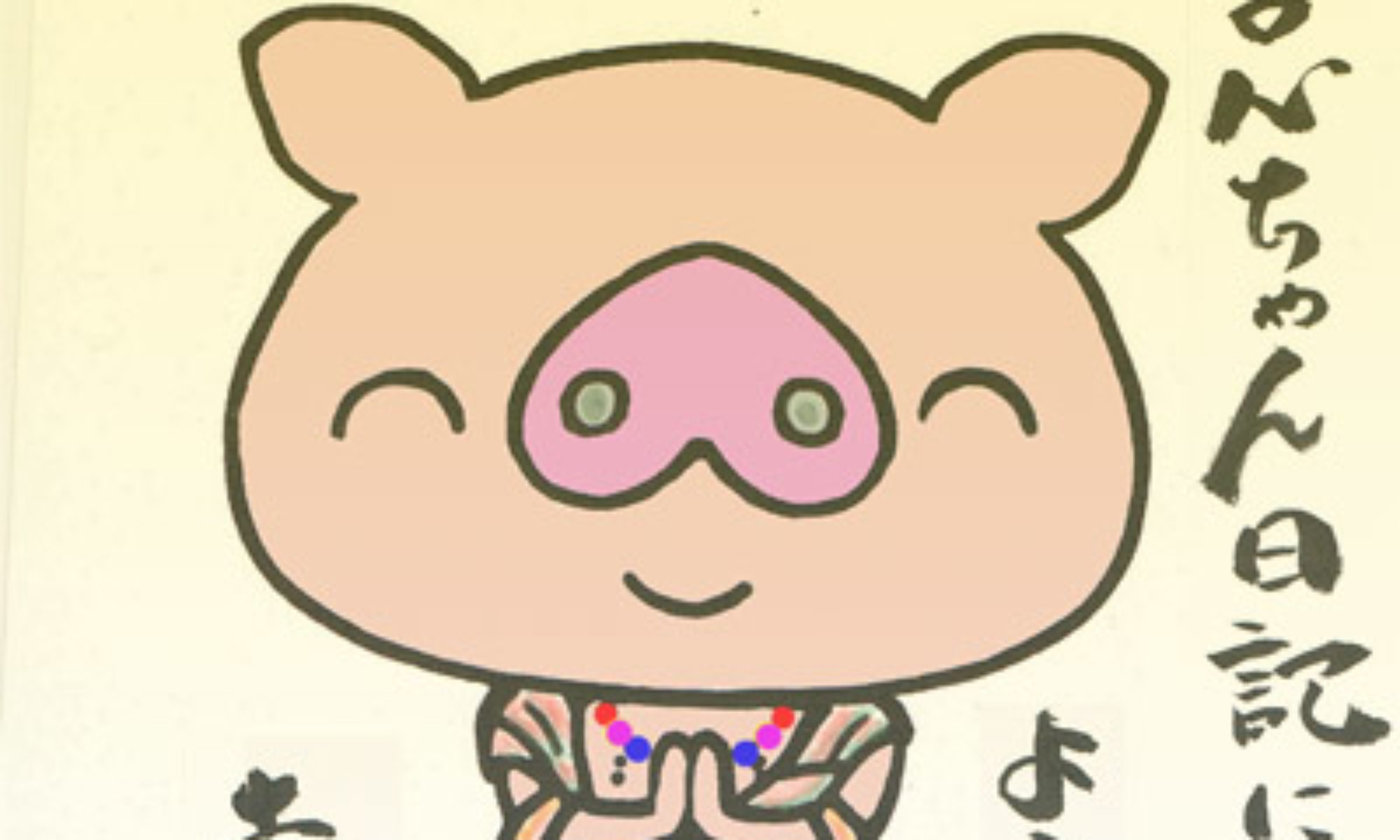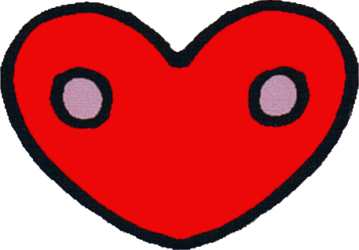靴底
毎度思うことだけれど、僕の靴の寿命は短い。
せいぜい半年。
1年持てば御の字だ。
「気に入るとそればかり履く」
と、言う「着たきりスズメ現象」もあるとは思う。
でも気に入らないのは、靴底が片減りし過ぎてダメになることなのだ。
かかとの外側ばかりが極端に減ってしまう。
そのうち外側に足が取られ転げる。
そんなことで靴の屍を累々と作ってきた。
ほんの子供の頃、墓参りの帰り道のことだった。
いとことじゃれあいながら先を走っていると、後からついてくる母親と親戚の会話が耳に届いた。
「うちの子ガニマタだから」と自虐的にも聞こえる話し言葉に少なからず幼心に傷となった。
当時は意味もわからない言葉だったのに。
ただ、「ガニマタ」というイントネーション的に、あまり良い言葉ではなさそうであると直感したのだろう。
子供の耳は敏感だと言うことを親は気付かないといけないいい例である。
今年になって去年の夏頃から本格使用を始めた皮靴のかかとに穴が開いた。
またかと思いつつも、もったいないという思いと「ガニマタ」の記憶がフラッシュバックする。執念深い奴である。
この機会に少し調べてみようと思った。
靴の減り方には整体的な部分があるようで、歩く理想的な減り方と言うのもある。
かかと辺りと親指の付け根辺りの減りがあるのが「歩く」という行為において、体重移動の正常な減り方らしい。
http://www.tiger-japan.co.jp/h_report/008_report.html
が、僕の靴は極端に片減りだから、あまり芳しい状態ではない。
どうやら、靴の減り方の原因にはこの「ガニマタ」というキーワードが少なからず原因となっているようである。
他のサイトには「丹田に力の入らない歩き方をしている」とも書いてあった。
今度はへそ下一寸にも意識をしながら歩いてみようと思う。
赤い・・・玉

右がルビー
左がジルコン
ルビーの方の色は、今までなかった色です。
玉からの製作なので、2ヶ月以上かかりそうです。
浅草のそら

ぼくの初日の出
朝のウォーキング。たいした距離じゃないけれど・・・
三日坊主になるか、一日ぼんずになるかしれないけれど・・・


桜橋からの眺め。
案外と走る人、ウォーキングの人、散歩の人の多さに驚いた。
東京マラソンの募集の多さに日本っていつからこんなにマラソン人口が増えたのだろうと思っていたのだけれど、僕が歩くより遅いジョギングのおじいちゃんの、せっせと走る姿に健康志向なのだと思うと同時に、先行きの見えない政情不安定の日本で、もし病気にでもなったら・・・という不安が健康志向の根底にあったりして・・・
などと考えてしまった。
うがった考えだろうか。
へ~
太極拳をする人達もいるんだ。

浅草のそら

お客様と一緒に歳をとるということ
Mさんが店におみえになった。
気が付けば二十年来お付き合いしてさせていただいている。
仏さまを観るのが大好きで、ずっと観音様にも通い続けている。
ちょっと前までは、巡礼にも暇を見つけては出かけいた。
もう八十の坂を超えるが、しゃきっとしていて一人暮らし。
ここに来ると「お話しちゃうのよね」
と、照れ笑いされながら何度も頭を下げて帰られる。
そんなに気を使わなくてもいいのに・・・
うさぎ屋のドラ焼きがいつもMさんの手土産。
うさぎ屋の包みがあると「Mさん来られた?」で99.9%間違いない。
ぬる温かい風はいやと、冬は絶対に暖房をつけない。
「だからこんなになっちゃうの」としもやけした鼻の頭を指差した。
夏は「クーラーの風はきらいなの」と35℃を軽く超えるであろう西日の差す部屋にあっても汗をかきかき過ごす。
そんな姿に凛とした古い日本の女性を見る。
江戸っ子の粋とも意地とも思う。
以前、若い頃の写真を拝見したことがある。
照れながらも僕のお願いに応えてくれた。
丸髷を結った若い姿に時代を感じた。
モノクロ写真は、もうセピア色になっていた。
でもそこには、僕より若いMさんがいた。
ぼくは人生の先輩の若い時代の写真を拝見するのが大好きなのだ。
今は老齢になられていても、
母の胎から生れ落ちた瞬間があった。
文字通りの青春があった。
恋に胸を焦がした時代があった。
子育てに格闘した時代があった。
そのすべてが先輩たちの容姿に刻印されているのだ。
その道程を想像するのが楽しくて、興味深くてならない。
Mさんも暦を刻んで80年。
家族のために懸命に身を粉にしながら戦前、戦中、戦後を生き抜いてこられた。
それ相応の年輪は確実に刻まれたけれど、
心はより人として深みを着実に増していった。
考えていくと時空と言う座標軸なんて、肉体の若さという尺度なんて、なんだか全く意味のないもの、虚しいものに感じてくるのだ。
結果としてMさんにいつも元気付けられる。
考えるに、元気の素を置いていってくださるゲストが実に多いことに気付く。
故に、こうして今まで商いの僅かでも続けられてきたのだと思う。
満開です。
ボケの花。

浅草のそら

ミニシリーズ完成
楠木と水檀で製作。
なかなかよく彫れました。

6cmに満たない総高なのに、よく刃物があたっています。