
店が閑散としているときは、すかさず手を動かす。
昨日とは打って変わって、お客様が少ない。
今できることは、今やらないと。
あ、そうだ。S女史の…
とにかくいろんなことが毎日

店が閑散としているときは、すかさず手を動かす。
昨日とは打って変わって、お客様が少ない。
今できることは、今やらないと。
あ、そうだ。S女史の…
忙しかった。
否。
忙しいing。
なのである。
結局、お昼は4時間ずれてしまった。
もうあきらめてもいい時間だけれど。
否。
諦められない。
意地でも食べてやる。
で、たちそばをかっ込んできた。
カレーうどんにしようかしらと、一瞬、脳裏をよぎったけれど、
ねずみは、食べたくないと、
心がブレーキを踏むことになり、
今日はおとなしく、好物のそばのみとすることにした。
僕が仏具店のまね事をはじめたころ、
まだ世の中は、好景気の真っ只中だった。
仏壇は置いておけば飛ぶように売れた。という時代は
とっくに過ぎてはいたようだが、
まだ、バブルの余波を受けて、国中がまだまだ乱舞し
業界もまだまだ鼻息の荒い時代だったようだ。
ただ、土地神話は気をつけなさい、
という言葉もちらりほらりと聞こえてきてはいた。
当時の電話帳を見れば、
1ページ広告1/2ページ広告などこの業界の老舗たちが
ページを飾って、如実に景気を物語っていた。
僕はといえば、
資本も売り先もない中で、船出してしまったわけで、
広告を打つにも、チラシ1枚作るにも元手がない。
そんな、帆一枚で荒海を越えるが如く、無謀な舵取りだった。
ただ、唯一の財産は、後先考えない若さがあった。
情熱と、念珠つくりの技術だけは蓄積していた。
(もちろん技術は見よう見まねで盗んだのである)
そして、とにかく人が好きだった。
10坪にも満たない店には、仏壇を置くスペースなんて
猫の額どころか、ねずみの額ほどしかなかった。
でも、そうした環境が幸いした。
当時、念珠や、香は、他店では、
仏具商として体裁をたもてばよい商材だった。
店の隅に申しわけ程度のつけたし商材であり、
1円単位の利益なんて、必要のない利益だった。
どーんと仏壇で利益を確保すればよかったのだから
3割4割引きで売られる店もあった。
そうした脇商品を、あえてメイン商材としてスポットを当てた。
正確には、「当てざるを得なかった」と言うのが本音でもあった。
もし、それ相応の店舗広さと資金があったとしたら、
「念珠堂」という名前すらなかったかも知れない。
他を見渡してみても、そんな店は、当時一軒もなかったと記憶する。
高額な仏壇が飛ぶように売れるそんな時代に、
あえて、手間のかかる利益の薄い商材を、
メインに選ぶなんて、気が知れないというところだろ。
すぐに消えてなくなると思われていたかもしれない。
自分に恐怖感はなかったかといえば、うそになる。
けれど、それ以上に、「自分にはこれしかない」
切羽詰った、どん尻の開き直りがあったし、
若かりし頃、生死の境をうろついたとき、
生きた仏教には、逢えなかった苦い思いを
念珠という手ごろな法具に賭けてみたくなっていた。
今に至った。
「もうだめ」が幾度あったか知れない。
が、そのつど不思議な出逢いによって、必ず救われてきた。
筆舌に尽くせないと言う表現があるが、文字通りなのだ。
法具を意識させていただいてきたおかげだろうか。
さてさて、今日は、どんな出逢いがあるだろう。
両替用の500円玉を崩した。
(銀行からは50枚がPPで巻かれて棒状できます)
全く気付かず半日たって・・・
お客様を相手におつりを渡そうと
「ありがとうございました」ああああっと。
あれ?やけに光る500円玉。
目の悪い僕にも柄の違いが遠目にわかる。
また、500ウォン硬貨が混じってる・・・
と思いきや。
「なんじゃこりゅあ」

南極観測・・・
記念硬貨じゃん。
ざっくざく(と言っても半数)が、記念硬貨だった。
万博記念硬貨まで含まれていた。
おつり用に使われるなんて・・・
こんなこと初めて。
でも南極記念硬貨なんて知ってました?
我が店は何でこんなにめぐまれているんだろう。
○○顧問が、本当に多くいてくださるのだ。
どう探しても見つからない梵字。
お願いしまあすの一言で、事細かに調べてくださる。
人の縁ほど宝物はない。
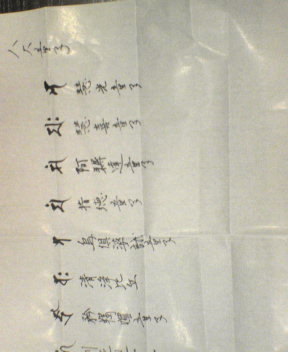

念珠の仕立で目を寄らせていると、
「よ!」っとばかりに肩をたたかれる。
向島のM先生だった。
80を越えてなおエネルギッシュなのだ。
写仏を教えて長い。
ご本人も高野山に上がり
お坊さんたちを指導するほどの技量を持つ。
老齢にもかかわらず、毎週、和歌山と東京を往復する生活を
10年近く続けた。
向島からここ浅草までも、自転車で桜橋を渡って川沿いに走って来る。
舌を巻く。同じ年齢になった時、自分はできるだろうか・・・と。
今日も、鎌倉十三仏を徒歩で廻ったその足で表装依頼のために
もちろん朱印をもらう、まくり(掛軸の画の部分)の
十三仏は、M先生お手製のものである。
恩人の葬儀のため、寝ずに書かれたと言う。
うちの店には、「難波敦朗氏」の仏画が数点、壁を占領している。
もし氏が体調を崩さなければ、写仏の教室を始める予定だった。
亡くなられた後は、数週間、ぼくの魂は、空中分解状態だった。
それだけに氏の画には、思い入れがある。
「またいい仕事しようね」そうおっしゃった言葉が今も耳について離れない。
店の真ん中で十一面千手観音が鎮座しているが
店の守り仏なのである。
M先生、実は、氏の数少ない弟子の一人なのである。
その話になると、いつも「不思議やね・・・」と
お互い感慨深くため息をつくことになっている。
「本当ですね」
これもぼくの決まり文句なのである。
「どこでどうつながっているかは、わからないよ」
「だから、誠実に一つ一つのことをこなしていくしかないんだよ」
これもM先生の決まり文句。
やんちゃだった若い頃など
微塵も感じない慈愛の目でいつも笑みを残し、
「えっこらしょ」とふたたび自転車を走らすのである。

正月も終ろうとするころには、なでてくれる皆の手のおかげで
いつもピッカピカになっているょ。
これがぼくの本当の姿さ。
人の手とは、
凄いもんだと、ことさら感じちゃう。

みんなの手の暖かさを、うんと感じたお正月でした。
まだ浅草はごった返している。
「ちょっと人混みはね・・・」
と出控えていらっしゃる皆さま。
せめて店内だけでも・・・
(あ、どうでもいいって)
