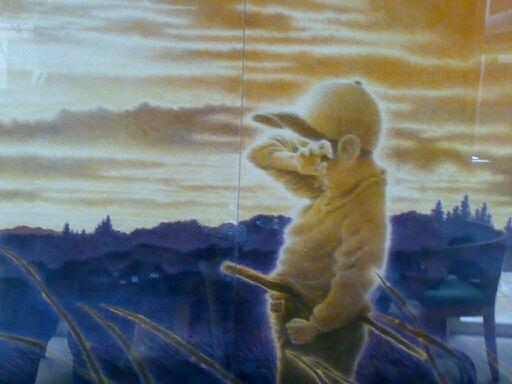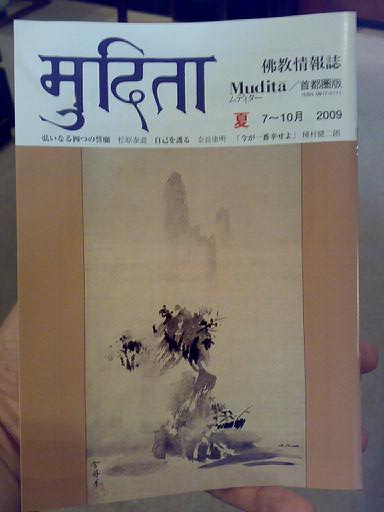最近盛んに加齢臭が取り沙汰される。
「お父さん何だかにおうよ」の一言で、
最近自分でも気になり始めた。
香りの商売をやっているからと言うわけでもないけれど、もともと匂いには敏感なのだ。
でも、いざ自分の匂いとなると、なかなか気が付きにくい。
親しい間柄だから忠告してくれるが、実際どうなんだろうとちょっと慄いてみたりもする。
ところで、加齢臭というが、若い頃に発散する匂いはなんて表現すればよいのだろう。
以前、上さんは塾を経営していた。
会社の二階が夜間に空いているのはもったいないと10年ほど続けた。
もともとはギャラリーができるようにと手をかけて作ったスペースなのだけれど、塾を開くにはちょうどよいということで、子供相手にはもったいないと思いつつも、泣く泣く上さんに明け渡した。
お香の香の立ち込めるムーディーな空間が、次の日から蛍光灯ぎらぎらの学びの館と化した。
子供たちもそれなりに集まって比較的優良塾となった。
朝の掃除は僕の分担だった。
ある日、二階に上がると、何とも表現のしようのない匂いが漂っていた。
「なんだろう・・・」
ガスでも漏れているのかな・・・
生魚とボンベのガスがまじったような匂い。
異臭である。
あいにくこのビルには都市ガスは使われていない。
じゃ何?
全ての窓をオープンし、匂いを追い出し、お香をいやというほど焚いた。
次の日も、その次の日も。
でも日曜になると匂いはしない。
日曜は塾は休みだった。
ということは塾が原因?
疑念が湧いた。
次の日ちまり月曜日に塾の営業?中、二階にあがってみた。
うわ!
咽てしまうほどの青臭さ。
異臭の元は子供たちから立ち上っている。
初めて気がついたのだった。
「青臭い事と言うなよ」とは言うけれど、ほんとに若いと青臭いんだ。
そういえば「青春」とも言うしな・・・
匂いが脳に働きかけて、人体に現象を起こさせることはフェロモンの実験に代表される。もしかしたら、年齢ごとに違う臭気を吸うことで、お互い何らかの補完関係、関わりを持っているのかもしれない。
青臭さは、老人の活力の元になっていたりして・・・
すると、三世代で暮らすのはよいというのは情緒的な面だけではないのかもしれない。
なんて・・・たわいもないことを思いながら、線香に火をつけている。