義理の兄が若きころ好きだった曲。
姉も影響されてよく口ずさんでいた。
「春夏秋冬」も良く聞かされた。
心象を素直に現す名曲だと思うが、曲の内容云々ではなく、
がらっぱちな歌い手が好きではなかったことと、
姉が心寄せる者への感情の波の中で、
坊主憎けりゃの論理で一把一からげにアレルギーを起こし、
人も曲も全く寄せ付ける心を失っていた。
この歳になって、気付くと口をついて出る。
どこか詩に共感するようになってきたのだろうか。
TONちゃんの勝手な思いをいつも考える、お客様のこと、浅草念珠堂のこと。。。
義理の兄が若きころ好きだった曲。
姉も影響されてよく口ずさんでいた。
「春夏秋冬」も良く聞かされた。
心象を素直に現す名曲だと思うが、曲の内容云々ではなく、
がらっぱちな歌い手が好きではなかったことと、
姉が心寄せる者への感情の波の中で、
坊主憎けりゃの論理で一把一からげにアレルギーを起こし、
人も曲も全く寄せ付ける心を失っていた。
この歳になって、気付くと口をついて出る。
どこか詩に共感するようになってきたのだろうか。
この10月から台東区は、ゴミの集荷方法が変わりました。
今までの可燃ごみとプラスチックゴミの分別がなくなりました。
そこで二日目の感想。
正直なところ、ゴミながらも、無分別の混合集荷は気持ちが悪い。
玉石混交に感じてしまう。
この同じゴミ箱に何でもかんでも捨てる行為がまず第一の関門。
混じったごみを見るのが第二の関門。
気持ちの悪さを誘う。
何年も続いた分別ゴミの習慣は、意外にエコ意識を植え付けてくれた。
可燃ごみにピニール製品を見つけられたら、集荷しなかったのだから
俄然出す側の意識は育つ。
こうなるとは予想していたけれど、気持ちの悪さは子供ですら思っているみたい。
いや、子供だからなを思うかもしれない。
混合ゴミでよいというのは処理場の理由だったり、
焼却炉が高性能になったからという理由なのだろう。
けれど、住民に育ったエコ意識を落とさせない配慮が大事なのではと思った。
ビニールやプラゴミなどは、貴重な石油製品。
集荷場に集まるそのゴミの量を見るにつけ、「これではいけない」意識が自然と芽生えてくる。
これだけ石油を無駄にしていると認識できるだけでもエコ意識と思うのだが・・・
水際が自然に啓蒙すされるよい機会なのだと改めて知った。
これでは精神衛生上良くない。
我が家では今までどおり、2系統に分別し続けることにしようと思う。
夢をみた。
小学校3年生のときの担任のN先生の子供に涙ぐみながら依頼された。
「父は非業の死をとげたのです。
その思いを解決して下さい」。
N先生は、元特攻隊の変わり者だった。
母と同じ年のはずだから、志願兵でぎりぎりの出陣だったことになる。
沖縄戦(だと思う)で途中エンジン故障のため引き返し不時着し、そのまま終戦となり九死に一生を得た(無念の涙を呑んだ)。
復員し、代理教員となり国語の先生になった。
結婚したが子供に恵まれず、その愛情を余すことなくぼくらに振り向けてくれた。
熱血教師は、軍隊式だった。
宿題を忘れた、間違ったことをした等と言うときは男も女も差別なく、即ビンタであった。
僕は何度そのグローブのような平手を食らっただろう。
バケツを持って廊下に立たされた。
忘れ物をすれば、走って取りに行かされた。
職員会議で何度もつる仕上げをされたと後で聞いた。
じゃあ、よほど恐怖教室だったかと言えばそうではなかった。
休み時間には生徒の中にいつも溶け込んでいた。
生徒の話に反応して猿のような赤ら顔をさらに赤くし、細い目を目をくしゃくしゃにしながらいつも笑っていた。
子供たちは、畏れながらも先生の愛情が充分わかっていた。
帰り間際になると、教員になって覚えたオルガンを楽しそうに弾きながら、
「お山の杉の子」の歌を「昔々その昔、しいの木林のすぐそばに♪」と合唱した。
いつか会いたいと思っていた。
その娘の頼みである。
「父の非業の死」・・・何だと言うのであろうか。
彼女の口から事情を聞いて七つ整合性が取れない話を確認した。
僕が指を折りながらもう一度復唱したところで、
「チン♪」という甲高い音で目が覚めた。
息子が夜食がわりに牛乳を温めた電子レンジの終了音だった。
本を読みながらいつの間にか転がっていたのだ。
「あやつられた龍馬」「幕末維新の暗号」と謎めいた本ばかり読んでいるから、そのストーリーに染まってしまったのかもしれない。
もう一度寝ようと横になりはしたのだが、ふと思い出した。
恩師は、50を間近に念願の子宝を授かった。
女の子だった。
鬼が神になったと風の便りに聞いた。
一人娘。ぼくよりもちろん年下。
おや?そっくり当てはまるではないか・・・。
目が冴えて眠れなくなってしまった。
読みたい本にたどり着かない。
近代戦記ものを何冊も読み続けていると、
無性に維新の時代が読みたくなる。
篤姫の時代を読みたくなり、最近本屋でちらっと見た
「小松帯刀」の本を買いに出かけた。
パラパラとめくっている間に、その脇に平積みしていた、
「今売れています」のポップに惹かれて手が伸びて、
会津藩の最期を書いた星亮一の「偽りの明治維新 」を発作的に買ってしまった。
薩長土肥連合に最後まで抵抗した会津の悲惨な史実に驚嘆した。
このままでは片手落ち、バランスが崩れるとばかりに、
官軍側の視点の本をとも一度「小松帯刀」の本を求めに行く。
パラパラめくっている間に、同じ歴史本コーナーに置いてあった
「あやつられた龍馬」の表題に龍馬好きの僕としては自然に手が伸び、
見過ごせず先に買い求めた。
フリーメーソンの暗躍によって明治維新が行われ、
龍馬暗殺の真犯人像にまた驚嘆しそれもありなんという思いで本を閉じた。
も一度本屋に出かけ、再び「小松帯刀」の本をパラパラめくっている間に「幕末維新の暗号」の表題に誘われて、また当初の目的ではないものが手に入ることに・・・
いつになったら目的に達するんだろう・・・
両方買っちゃえという手もあったな・・・
近所に住む元朝日新聞天声人語執筆員のおじいちゃんに、
「見なさいよ」と念を押された知覧のドキュメントを拝見した。
冒頭から泣けて泣けてしかたなく、
家族の手前、テーブルに顔を横に倒しくっつけたまま、
最後まで顔を上げることができなかった。
以前靖国神社の遊就館の売店で手に入れた「命の言葉集」を買い求め
特攻で散華した若者の遺書を何度も読んだ。
読みながら、同情の涙を幾度も流した。
けれど、当時の最高学府を学ぶものたちも含め、
これほど非人道的な兵器によく乗ったものだと思った。
戦争とはそういうものだと言われればその通りなのだが
否応なく応えなければならない時代の空気はもちろん考えなくてはならない。
そうした条件を差っぴいても考えをはるかに超越した何かを感じざるを得なかった。
あるとき当時の若者たちが何を望んだのかを知る機会を得る機会があった。
特攻に出たとしても、この戦争は負ける。
自分たちが散華したところで戦争の結果がどうなるものではないと百も承知していたという。
負けることはすでに肌で感じ終局は変化できずとも、後に続くものに託すと。
自分たちが散華することで、後の日本人がその魂を受け継いでくれるだろうことを信じ飛び立つのだと。
そういう彼らの観念を知ったとき、
ただ可愛そうだと思う、ヒューマニズムだけで理解してはいけないのだと感じた。
現代を生きる自分たちには責任がある。そう感じた。
だれかが置いていかれたご縁玉。
だいたい察しはつく。
いつも帰りがけ外の小僧さんの頭をなでて手を合わせて行かれるあなたでしょ。

粋なことをされますね。
子供時代、お彼岸と言うと、父の墓参りが一大イベントだった。
当時住んでいた、横浜の白楽から父の墓のある西東京の田無まで、子供心には結構長い家族旅行であった。
渋谷までは東横線で一本だが、西武新宿線は当時、高田馬場を始発としていた。
ゆえに渋谷→高田馬場間は、国鉄を使わなければならなかった。
当家はどうやら全員が方向音痴のようで(要するに母譲りということなのだろう)渋谷駅が近づくとひそひそ話しが始まる。
「絶対離れちゃダメよ」
「迷っちゃうからね」念には念を入れて母は子供に注意する。
子供は子供で「お母さん迷子にならないで」と心に思っている。
母の緊張はこちらにひしひし伝わってくる。
過去何度も乗り換えに失敗している因縁深き駅なのだ。
だから乗換えが複雑な渋谷駅を前に手に汗を握る緊張のひと時なのだった。
高田馬場駅で国鉄から西武新宿線への乗り換えは実に楽だった。
ただ、西武線は当時とにかく時間がかかった。
子供心にも、そう感じた。
目的の花小金井駅の一つ手前で鈍行に乗り換えるのだが、これが恐ろしく待たされる。昔と言えど横浜市内の喧騒さと比べれば話にならない静けさだった。
亡き父が学生時代はたぬきに道案内されたと言う話もまんざらでもないと思う瞬間だった。
ひばりのピーヒョロローの鳴き声も聞こえてきて、なんとも牧歌的な風景でいつもここで眠くなった。
手入れが行き届いているとは言い難い草ぼうぼうの軌道敷きと、高圧線。弧線橋ではなく、駅構内の踏み切りで上下線の乗り換え(田舎の駅そのもの)、4両編成がせいぜいの短いホーム・・・
彼岸花が咲く川岸と相まって、今だに西武線=田舎電車が僕のイメージから抜けないのである。

浅草神社の歴史。
お祀りしている三社を訳あって調べています。
さすがに奥が深いや・・・
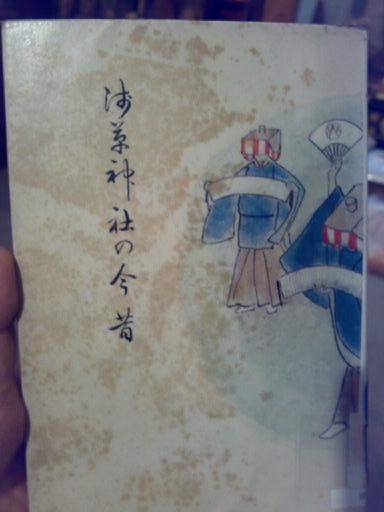
すっかり秋風の吹く一日でした。
日向に出るとこげるように暑いのに、
木陰に入ればすぐに冷ましてくれます。
「風に誘われるままに、どこかに出かけてしまったら?」
右脳は旅に誘う。
そうは行かない現実を慌てて思い出させて左脳は忠告する。
「やることがあるでしょ」
「こんな気持ちのいい日にくすぶってんの?」
右脳はアプローチをやめない。
「現実を見なさい」
左脳も負けじと水をかける。
「いい風だよ」
と右脳。
「店内にもいい風吹いてるよ」
と左脳。
「店長お直しですよう・・・」
店員の声に全てがかき消される。
頭の中で、こんな闘争がしばらく続くのかしらん。
こまったものだ・・・
空ばかり見る機会が増えた。
雷門の前ではそれこそ毎日。
おかげで、目線は地上よりいつも上を向くようになった。
下を見ないから躓くことも多くなった。
目線が上だから、ごちゃごちゃした町並みで仕切られた狭い空間より
開かれた空にいつも気が大きくなってくる。
それにしても都会では空が狭いな。
どうせ毎日見る空なら
こんなことに利用できないものかなと思ってしまう。