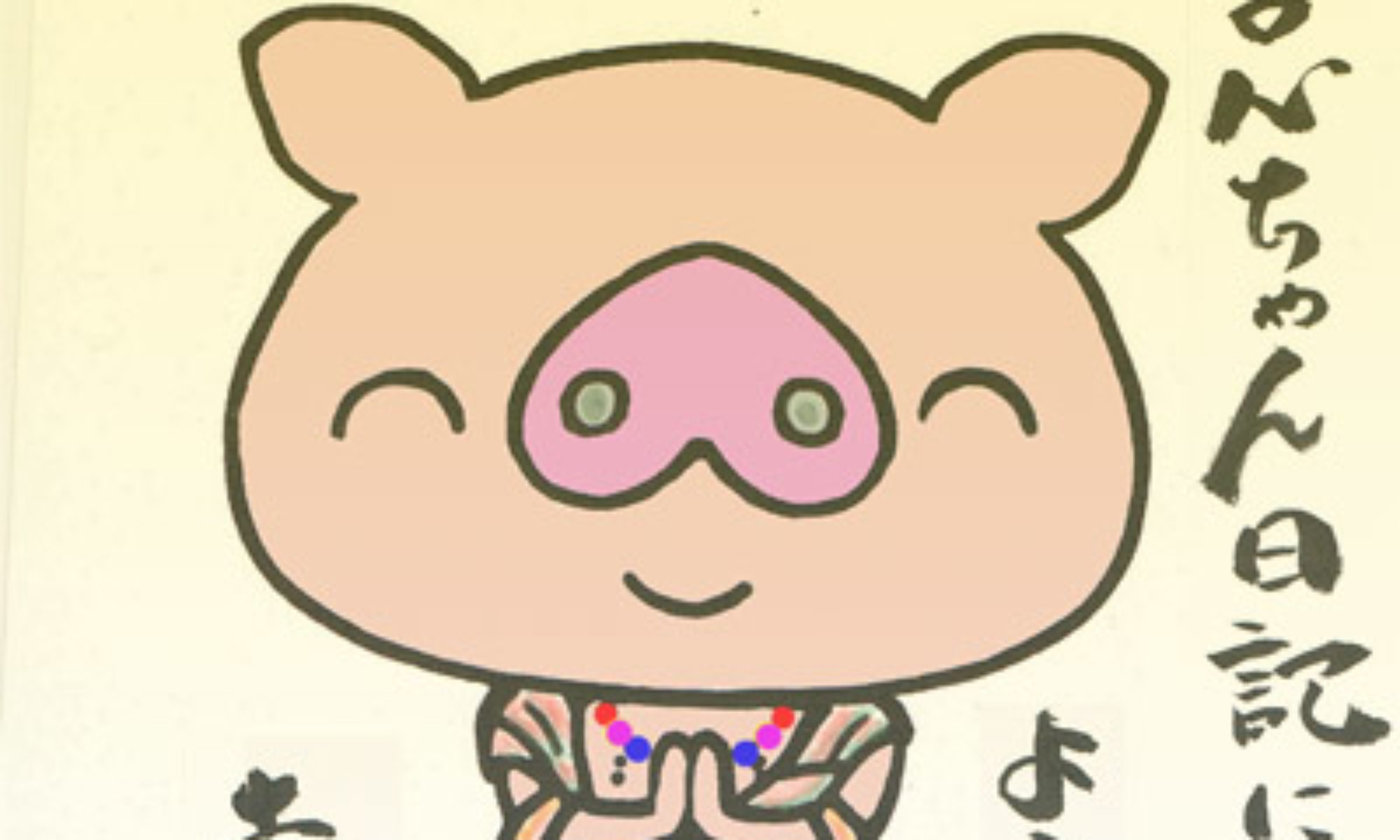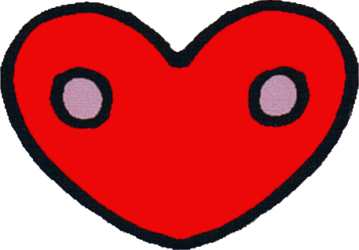富士山狂想曲を書いたら、
はじめての峠越えのことが頭から離れなくなった。
山本茂美の「あゝ野麦峠」女工哀史を読んで、どうしても行きたくなった。
19歳の夏のこと。
当時は、社会にひたすら疑問を持っていた時期だった、
胸を打たれて、衝動的に電車に飛び乗った。
横浜から名古屋経由で高山までは輪行(自転車をばらして持ち運ぶこと)だった。
レーサーシャツに短パン、レーサーシューズのいでたち。
今思うと、何とも恥ずかしいいでたちだった。
(今は珍しくなくなったけれど)
当時としては、かなり突拍子も無いスタイルだったろう。
夜明けと共に高山の駅に降りたった。
ロードレーサーを駅前で組み立てた。
余分なパーツが無い分、
あっという間の組み立てだった。
けれど走り始めたのは、多少日が高くなっていたように記憶する。
スローなスタートだった。
女工哀史にならって、本番の野麦峠の前に美女峠という小さな峠を越えた。
なだらな上り坂。難なく越えたがエネルギー消費。
ただ、本命の野麦峠へのアプローチに入る頃には、
正午を過ぎていた。
真夏のこととは言え、山越えの時間としては若干遅かった。
飛騨側の路面は、多少荒れてはいたけれど、舗装路の上り坂。
寝不足の体には、少々つらかった。
途中、水のみのため、
写真撮影のため、
と称しては休み休み、峠に立ったときは、
日は、西に傾き始めていた。
すでに太陽はオレンジ色に染まり始めていた。
建て直されたお助け茶屋は、予想に反し近代的で
お茶を一服いただいて、早々に小屋を出た。
席を立つころは、すでに3時を過ぎていたと思う。
泊まりの設備もあったようだが、仕事が待っている
意地でも一日で越えたかった。
これから松本側への下りが始まる。
山道は、あっという間に日が暮れるから、不安もよぎったのだが。
「下りだろ。大丈夫。大丈夫」
自ら鼓舞し、泊まり客の間をすり抜けて
弱き心を振り切って、松本側に滑り出すことにした。
さあ・・・。
ここからが地獄の一丁目の始まりだったのだ。
初夏とは言え、山の日暮れは極端に早かった。
ロードレーサーで行ったということは、
夜間を走るつもりはなかったのだ。
携行品と言えば、小さなリュックに、
非常食と雨用のウインドブレーカーのみ。
そんな状態だから、もちろん前を照らすライトなど
準備しているはずもなかった。
今となっては、どうしてそんな軽装で出かけたのか、
全く思い出せない。
ライトを持っていなかったことは、
文字通り「後悔先にたたず」だった。
峠を少し下ると、数メートル先で舗装は切れた。
「関」はさすがにないが道路の状況でそこが県境であることがわかった。
曲がりなりにも簡易舗装の飛騨側から、一気に江戸時代に逆戻りした。
道は両側がうっそうとした熊笹で覆われるから薄暗い。
女工悲史では、この熊笹の獣道を越えて行った事が描かれていたっけ。
道幅こそ当時よりは格段に広かったが、
車一台やっと通れる細い九十九折の林道だった。
しかも急坂だ。
地道の路面は荒れて、しかも、こぶし大のバラスが、
不均等に敷き詰められていた。
山の伏流水で洗い流されたのだろう、ごつごつした岩肌が
所々露出し、ときには抉られて、その落差で自転車もろともこけた。
とても、レース用の細いタイヤで走れるような代物ではなかった。
試しに、空気圧を高めに入れて、数百メートル走りはしたが、
見事にパンクしてしまった。
(レーサー用のタイヤは、パンク修理に針と糸が必要なのだ)
ここで、予備タイヤを使ってしまった以上、
松本までの数十キロをもうパンクさせるわけにはいかなくなった。
予想外の展開に、十分もかからず駆け抜けるところを
1時間以上歩いて下ることとなった。
しかも、金属プレートを打ち込んだ、
レーサーシューズで。
そんなときに限って、「ああ野麦峠」の一節が脳裏を掠めるのだ。
故郷の土を踏めずに亡くなっていった女工たちの心境が
みごとに湧き上がってくる。
道は狭く、熊笹に覆われて、足元もおぼつかない。
なんとも心細い話であった。
ついでにカラスまで、不気味に鳴いて驚かす。
ようやく浮石のなくなり、舗装のある地点まで下がると、
日はとっぷりと暮れて、夕闇が迫っていた。
本来なら松本までの20kmを越えるダウンヒルを
豪快に楽しむはずだった。
しかしすでに闇。
人っ子一人いない山の中。
ライトは、腕に付けるレフ(赤色灯)のみ。
ままよと下った。
泣きっ面にさらに困ることが起きた。
新月だったのだ。
全くの暗闇で道が見えなくなった。
不幸中の幸い、舗装路に出た。
舗装路のセンターラインが薄っすらぼやけて見える。
けれど、道は渓谷沿いに下るので、一歩間違えば「ドボン」
恐ろしい話だ。
泣きたくなるとは、こういうことを言うんだろうな。
昼間なら、気味の悪い随道も、
このときばかりは、水銀灯のオレンジ色の光に、
九死に一生を得る心持ちだった。
ダムを越え、若干の上り下りをとにかく、
猛スピードで通過した。
人は、疾走する僕の形相をどんな姿に見ただろう。
松本の町の明かりが見えたときは、
ほぼ放心状態にあった。
こんな思いをしはずなのに、
また走りたくなるとは、どういう構造なのだろう。