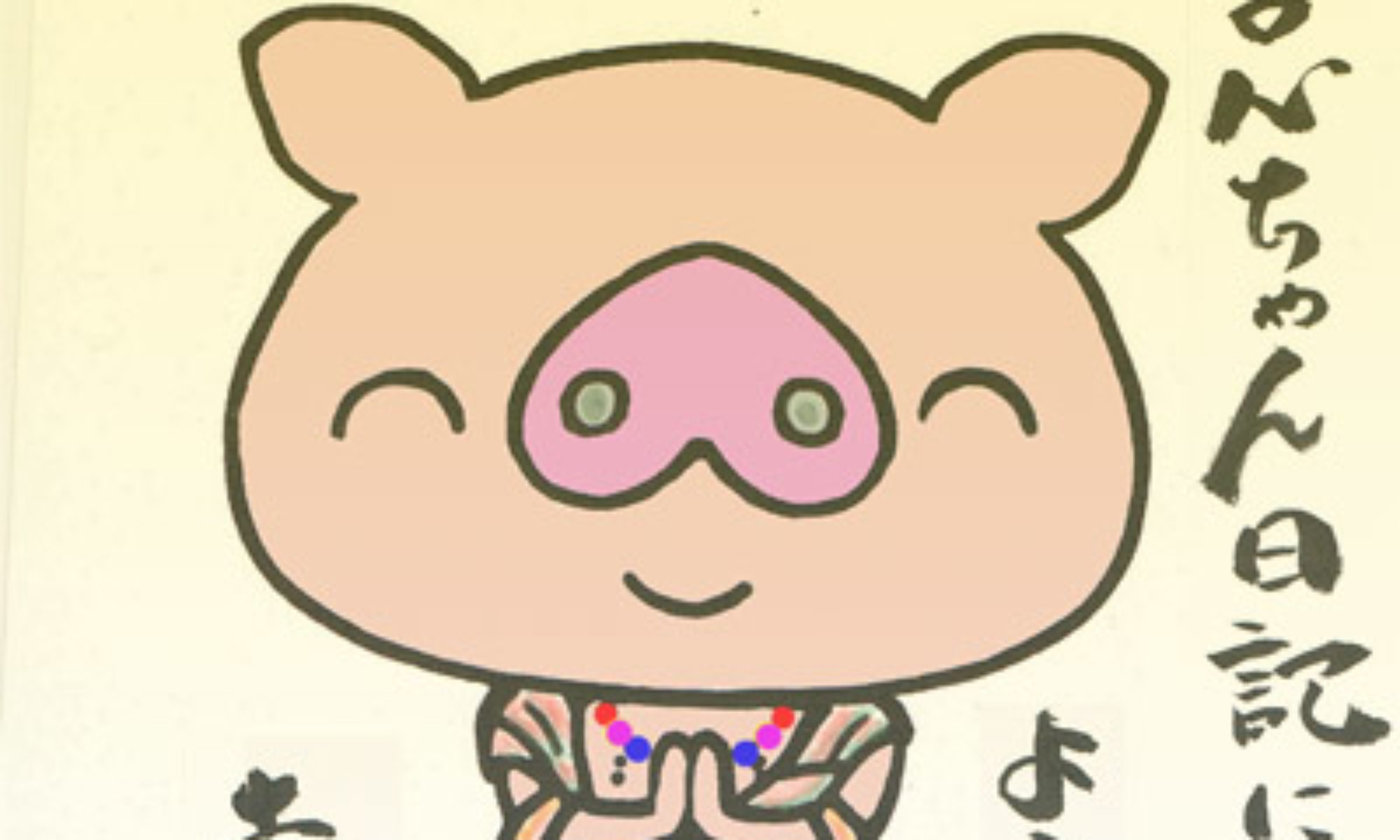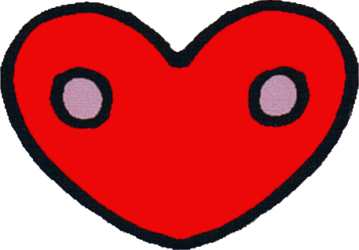雨




浅草のそら

伝法
待機説法(たいきせっぽう)と言う言葉がある。
お釈迦様は苦行の末に真理を見出す。深遠なる悟りの世界を語りきれないと一度は諦めかけながらも、梵天勧請(ぼんてんかんじょう)によって、法を人々に説くことを決意される。80年の生涯は文字通り法を説き伝える(伝法)ための人生だった。
お釈迦様の説かれた法は、極端な言い方をすれば、ある人にはカラスは黒いと説き、ある人には白いと説くようなものだった。
言葉の表面上をのみ見れば、全く異なる表現で現され単純に比較すれば戸惑う。
字面だけを書き連ねれば矛盾だらけの結果となってしまう。
どうしだろうてか。
それはお釈迦様は、文字(経)を残されたのではないからだ。
残したかったのは、相手の心のありようなのだ。心の救済をされたかったのだ。
千変万化する人の心模様に対し、導き方も千変万化するのである。
つまり、待機説法とは救済される人それぞれの心の状態に応じ、求めるものに応じ、理解度に応じ、説を変化させながら道を説かれたということなのだ。
土に生きるS師に久しぶりにお逢いした。
師を通して縁をもつことのできたMさんの誕生日をしましょうと集まった。
師は在住している地元で不思議な会を設けていた。
(組織論でものごとを進めるくせのあるものには「不思議」と思えるのだが)
月に一度自由に人の集まる場を提供しているのだ。
そこには悩みをもちよって参集されるのだろう。
解決の糸口を求めに人々は集まるのだが、そこに説法はない。
大上段で振り下ろされる鉈(なた)はないのだ。
あるのは参集した仲間たちの自由な同情があるのみだ。
でも生きる智慧はその中からこぼれんばかりに生まれる。
智慧は人がそれぞれ持ち合わせているのだ。
そんな話を聞きながら、説く仏教ではなく、痛みに、悲しみに添う仏教と言うことを
学ばされた。
さて、80を有に越えるM氏の若かりし頃のエピソードとなった。
泳ぎの達者な彼は、昔、二度おぼれている人を助けた。
一度は実の妹を助け、一度は友人を助けた。
80を越えるというのに矍鑠としておられるので若い頃はさもありなんと想像するに難くなかった。
「助けるときはね、その人の背後に潜って回って、抱きつかれない様にしてこうして岸まで押したのさ」身振り手振りで話してくれた。
子供時代、二度溺れ死に損ねた僕としては、それだけでも尊敬に値する話なのだが、聞きながら、真理が隠れていることに気付かされた。
人の悲しみに添う仏教とはそのようなものかと沸々実感させられてきたのだ。
「正しい生き方とはこうだ」とすっぱり切ってもらうのも気持ちよいときももちろんある。
しかし「言わぬが花」も人によっても、また時としても必要なのだ。
だからこそ待機説法なのだ。
「語らず伝える」は、仏教者の・・・いやいや、
仏教に限らずあらゆる信仰の最低のスタンスでなければならないのだろうと感じた。