明日からまた寒くなるんだって・・・
今日一日だけの休息・・・。
でもね・・・
ちゃあんと春は近づいているよ。

樹木はしっかり芽吹きの準備を怠らないさ。
思わされるねえ。
心次第で、日の光にも暖かさを感じるもの。

この風景にも新東京タワーが顔を出すようになるかも。

あともう少しで桜の下でをいやでも実感する風景になるよ。

明日からまた寒くなるんだって・・・
今日一日だけの休息・・・。
でもね・・・
ちゃあんと春は近づいているよ。

樹木はしっかり芽吹きの準備を怠らないさ。
思わされるねえ。
心次第で、日の光にも暖かさを感じるもの。

この風景にも新東京タワーが顔を出すようになるかも。

あともう少しで桜の下でをいやでも実感する風景になるよ。

錫杖本体を古代仕上げにして黒柿の柄をつけました。


目黒の若旦那との連絡は夕方に決まっている。
とても反応の良い方なので、つい挑発したくなってくる(失礼)。
天台宗の玉をこよなく愛されているので
手元にあるものは、あるもの、ないもの取り混ぜながら
お話しを誘わなくとも、気持ちが通じている。
で、大平の天台をアップしようと
また、いたずら心が働いて、今日は二種お見せしたいと思った次第。
さあどうでしょ。
虎琥珀の大平天台。
なかなか渋いでしょ。


椰子の大平天台

昔の椰子は軽かった。とても軽快で好きな玉だったのだけれど、
仕入れルートが変わってからは、
玉がズッシリ重くなってしまった。
以前の椰子らしさは若干陰を潜めてしまったことは残念だ。
明日は沈香の大平をお見せしようかな。
最近、お客様と接していて時々返答に困ることがある。
「どれがいい香りなの?」
「伽羅は高いからいい香りなのでしょ?」
ん~~・・・
たしかに伽羅は僕にとっては好きな香りの一つだ。
けれど、1グラム一万円だからいい香りだと思ったことは一度もない。
ただ、好きなだけだ。僕にとって。
NHKの解体新ショーという番組で、香りの不思議をテーマにしていた。
匂いを嗅ぐと昔の記憶が他の感覚より特出して新鮮に蘇るのか、
ということをテーマにしていた。面白いと思った。
いつか取りたい資格に臭気判定士という資格がある。
その概論を読むと、まず匂いという不思議なメカニズムが紹介される。
匂いを嗅ぐと匂いにまつわる情景が誰でも想い出されることだろう。
それは音楽にしても、つまり聴覚から入る情報にしても同じことが言える
また、味覚も同じこと。
五感は、そうした過去の記憶と密接に結びついているのだ。
その中でも臭覚は、その情景のみならず、
その時の心理状態までも他の感覚を伴って複合的に引き出される所が他の感覚との違いなのだ。
何故そうなるのか・・・
答えを言えば、匂いの感覚は、古い記憶のメモリー装置であるところの
脳の海馬(かいば)組織にダイレクトに働くことがわかっているのだ。
海馬と感情をコントロールする扁桃体(へんとうたい)組織は隣り合わせて深く関わりあっていると言う。
だから、香り、匂いの断片が鼻をつくと、
それにまつわる記憶と感情部分までも複合的にフラッシュバックされるのだという。
小学校の6年まで車酔いとの戦いに明け暮れていた僕は、
トラベルミンなどという洒落た薬を飲むよりも、正露丸一本やりだった。
一途さは聞こえはよいが、母の正露丸信仰が万能薬として、
確固たる地位を占めていたに過ぎない。
遠足などバスに乗る機会には、
救急薬として必ず持たせてくれた。
だから、今でもクレオソートの匂いを嗅げば、
バスの車内の様子、「西海君かわいそう」「またかあ」「がんばれよ」などと外野の声も、友人の顔も、窓の外の風景も、手に取るように思い出す。
カレーの匂いを嗅げば、食卓の楽しさと団欒の暖かさ、
ひとりでモクモクと食べていても暖かい気分にさせてくれる。
人それぞれ、その香りに対するイメージは全く異なる。
いつもひとり寂しくボンカレーを煮て食べていた悲しい過去を持つ人ならば、カレーの匂いを嗅ぐたびに、なぜかしら、その寂しさが湧いてきてしまうからどことなく避けようとするだろう。少なくとも楽しい気分にはさせてくれないだろうから。
だから、お香は10人いれば10人、100人いれば100人、1000人いれば1000の嗜好が生まれて当然なのだ。
これは高い材料を使用して懇切丁寧に作ったのだからいい香りです。
これは京都の香司が創った伝統の香りなのだからいいです。
便宜上使用するときもある・・・
けれど本当は、ありえないと言うことなのだ。
自分にとって何がいい香りなのかは自分の心が知っている。
あなたにとっていい香りかどうかは、あなたの頭の中にある海馬に聞いて欲しいということなのである。
だから、万人がこれはいい香りと認められる香りは?というならば・・・
お母さんの香りとでもいうのかな・・・
金襴でオーダー製作。

丁寧な仕事だ(プロだもの当たり前かな)。
縦長だと、自転車でまわるときも楽そうだ・・・

便利に出来ました。
喜んでいただけるといいなあ。
一時はこんなだったけど・・・

激しく降る。

こんなに降る降る。明日は日曜日だというのに・・・

今、外を見たら、
もうやんじゃった。
天気一つで一喜一憂する、商人Aである。
店を一日閉め工場見学をさせてもらったが、
思わぬ副産物として、下町散歩の時間を与えられた。
当初は浅草から車を運転して全員を運ぶつもりで計画したが
集合の時間の早さに恐れをなし、現地集合となるにおんだ。
一人残される。
聞こえは寂しそうな余韻があるが、運転しない気楽さはありがたい。
なら自転車で行くかということを何気に口に出た。
自分の足で池袋までは行ったことなかった。
例の如くママチャリ号の出動と相成った。
片道14~5km程度だからたいした距離ではなかろうと思いつつ、
主催者が間に合わないとどうなるの。パンクしたらどうするの等々不安さも残るが
Aの仮面をかぶったB型人間は、エイと飛び出した。
東京と言うとどこまでも平坦なイメージがあるのだが、
自分の足を使うと意外とだらだらと坂道が多い。
最近国道何号線とか都道何号線という呼称から、
江戸通りなどの愛称の通りがよくなった。
それに伴う形で○○坂という古来の名称が復活してきて、「坂」が東京にはごまんとあることに気付くのだ。
車では、巡行速度4~50km。
路傍の道標も気付かぬままあっという間に見過ごしてしまうし止れない。
けれど、徒歩や20km前後の自転車からの目には、
面白いように様々な情報が飛び込んでくる。
以下道草の数々。
不忍池から観音堂を望む。枯れた蓮とすすきは無情を現すのにちょうどよい。

少し予定を早すぎたので、時間調整に護国寺に寄る。
本堂主任が変わってしまってからは、トンと縁がなくなってしまった。
警察出身の素敵な住職だったけれどどうしているかな。

雑司が谷では都電を待つ。

大塚でも都電を待つ。

寒椿が沿道を装う。
千駄木では、表通りを避け路地裏を走る。
こんなところにと思う袋小路に桜の古木と出会う。
花をつける頃にまた来よう。

上野ではコリアタウンをのぞき、
30年通う店に顔を出し好きなエゴマを仕入れる。

とまあ、思わぬ副産物が付いてきたけれど、
自分の住む町を違う角度で見られたのは収穫だった。
交通弱者に心配りのない道ということも含めて勉強になった。
何年ぶりだろうか。
今日は店を閉めて社内研修をした。
鎌倉の香司に行こうかとも思ったが、
まず香の素材や製作工程がわからないと
と言うことで、業界NO1の日本香堂の池袋工場に決めた。
断腸の思いで貼って出かける。
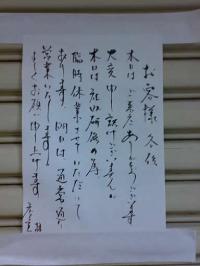
有楽町線の要町駅から歩いて数分の住宅街の中に
池袋工場は位置している。

店のみんなは駅で待ち合わせながら工場に集まる。
僕は自転車で現地集合。
浅草からママチャリでも40分あれば着いてしまうのだから
近い近い。
こんな都会の真ん中のしかも住宅街のまんまん中に香りの工場が、
どんとあるわけで、知らない人は、ホント驚くよ。
工場に近づくと以前と様子が違う。
外見は、日本香堂のNKロゴがあちこちで自己主張している程度の変化はあったが
何も変化しているようには見受けられない。
しかし・・・絶対何かが違う。
そう。
周囲に漂っているはずの線香の匂いが極端にしないのだ。
あとで工場内部を案内されて、ようやく納得することができた。
つまり、脱臭のシステムを駆使して、線香の匂いを表に出さない努力をしているのだ。そうすることで環境を守る努力をしている。


(材料の話し)(材料を練る工程を案内された)

製作工程を見学後、今度は場所を青雲記念館にかえて線香の素材のレクチャーを受ける。

普段は製品の姿となったものしか目にしないから、
なかなかここでしかお目にかかれない素材体験は貴重だ。
龍涎香(りゅうぜんこう)や麝香などは最たるものだろう。

マッコウクジラの結石だ。
消化されないイカのくちばし部分が結石化したの塊というだけあって、近寄って見るとまさしくその通り。


麝香鹿の香のう・・・
なかなかお目にかかれない珍品だ。
などなど、伽羅の数々も含めて、材料の豊富さには
何度見ても感心するばかりである。
さあ明日から、販売現場で何か変化あるかなあ・・・

なんでこんなにいいんだろう・・・
日本人の手によるものであることは間違いないのだが、
名のある仏師と言うことでもないようではある。
けれどバランスもいいし、
顔がいい。
この慈悲心を端的に眼に現せるというのはそう簡単ではない。

厨子も埃はかぶっていても、手がいい。
お釈迦様は人生を苦と見られた。
苦界からいかに脱せられるかと悩み苦行し悟られたのだ。
苦を理解した土台に四諦八正道の教えが生まれるわけだけれど、
そこに行き着くには、まずもって苦を骨身に沁みて理解されなければ
病に気付かぬまま薬は処方できないように、
行の処方もかなわないだろう。
苦については、四苦八苦という馴染みの言葉がある。
ほぼ慣例的に「仕事がさあ、四苦八苦よー」などと
冗談めいて使うほどののりになっている慣用語である。
けれど、これはれっきとした仏教用語。しかももっとも根幹部分の。
徹頭徹尾、骨身にに沁みないと、次に進めないのが人の性のようで
まだ余力があるうちは、べつの楽な道を探そうとする。
苦には生きる苦しみ。老いる苦しみ。病う苦しみ。死にいく苦しみ。
の四苦。
そして、愛せども離れいく苦しみの愛別離苦(あいべつりく)、憎しみ合いながらも離れられない苦しみの怨憎会苦(おんぞうえく)、求めつつも求めきれない苦しみの求不得苦(ぐふとくく)、こだわり執着から生まれる苦しみの五蘊盛苦(ごうんじょうく)の四苦を足して八苦になるというわけだ。
親友を自殺と言う形で失ったことで、
丸一年地獄の苦しみに苛まされたことが若かりしころあったが、
積極的に生きる姿勢の中から自分なりの生き方を発見できた
若かりし頃と違う生老病死苦があることをお客様から教えられてきた。
何度・・・契約の現場において、説明の最中において、納品の先において、嗚咽させられたことだろう。人目をはばからず泣いた。
この仕事をとおし、涙を飲み込むことを覚えたけれど、
「四苦八苦」のこの言葉。仕事を始めるときに軽く覚えた言葉は、
どんどん深層部分に染み込んでいくのである。
思いが深まるとは先人がよく言ったが、まさに当を得た言葉である。
言葉が深まるのである。
まだこの先いかほどの教えを、お客様から賜るのだろうか・・・