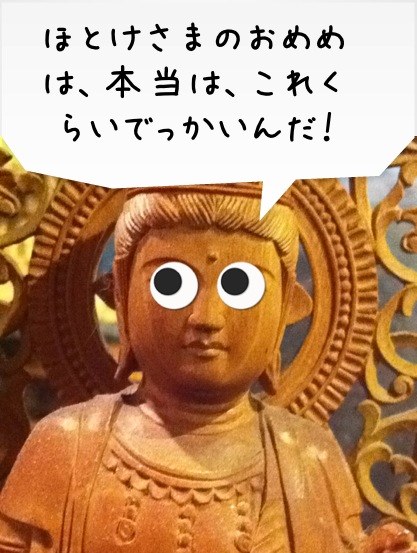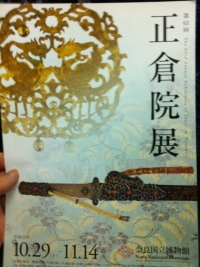一年前もこの時間。
パートさんたちが休憩を取り終わり、TONが最後に昼食をとっていた。
狭い部屋に弁当に口をつけた。二口、三口。
「ユッサユッサ・・・・」
あれ。地震。
つい先日も揺れたばかりだし、「またか」というのが正直な気持ち。
30秒くらい揺れたのだろうか、ジャブのような揺れはとどまるどころか、方向を変えて揺れだした。
「これは違うぞ」と思って、小部屋を飛び出した。
出たとたんに今までにない横揺れが襲ってきた。
縦長のショーケースは片足立ちしながら揺れている。
商品はそのたびに右に行ったり左に行ったり。。。。
香炉のいくつかが横っ飛びして足元に落ちた。
「ガチャン」
お客様を非難させなければと見るとパートの子と抱き合って出口付近で固まっている。
「外には出るな」叫んだように思う。
その後も仏像は飛び跳ね、仏具は転がり、念珠はフックからはずれ。。。
あれから一年か。
今のところ無事。
忘れようにも忘れられるものか。